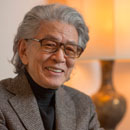五木寛之 流されゆく日々
-

連載11762回 我流をとおす生き方 <1>
今年も暮れる。 12月にはいると、カレンダーが音をたててめくれていく。 出版の世界では<年末進行>という例年の行事で、さまざまな雑事が押しよせてくる。師走とは、よくいったものだ。猫の手も借り…
-

連載11761回 ムラの形成と抵抗 <4>
(前回のつづき) 戦うことと、逃げること。 わが国では、最後まで抵抗して戦い抜くことを讃美する気風がある。 城と共に敗れて一族、自害する気風が悲壮感をもって語られることが多い。 しかし…
-

連載11760回 ムラの形成と抵抗 <3>
(前回のつづき) 惣村が成立すると、農民は惣百姓としての自覚と連帯の意識とともに、惣掟などを定めたり<自由の検断>と称される法的対処までも手にする場合もあった。 荘園制度の衰退にしたがって、自…
-

連載11759回 ムラの形成と抵抗 <2>
(前回のつづき) 中世というのは変動の時代である。鎌倉後期ごろから、地方の農村に<惣>という現象が生まれてきた。<惣>は<総>でもある。ひとつの集団意識といってもいい。 かつて、というか戦後の…
-

連載11758回 ムラの形成と抵抗 <1>
私が新人作家として執筆活動をはじめたのは、1960年代後半である。 当時はジャーナリズムの酷使に耐えて生き残ることが、プロ作家の条件だった。 その後、<休筆>と称して、しばらく小説を書くのを…
-

連載11757回 古い万年筆を修理に(補稿)
(前回のつづき) これまで、いくつかの賞の選考委員を長いあいだつとめてきた。 90歳を過ぎて、老害、という言葉を思いだして、退役を申しでたのだが、まだ半分ほどが残っている。 そのなかの一つ…
-

連載11756回 古い万年筆を修理に <5>
(前回のつづき) 私は極端な筆無精である。ほとんど病気といっていいくらいに私信というものを書けないまま馬齢を重ねてきた。 当然、書くべき返事を書かなかったために、人間関係をそこねたこともしばし…
-

連載11755回 古い万年筆を修理に <4>
(前回のつづき) 昨日、めずらしく万年筆の手紙を頂戴した。金沢のテレビ局、テレビ金沢の蔵さんからの連絡である。 若いプロデューサーだった蔵さんと一緒に<新金沢百景>という番組を立ちあげたのは、…
-

連載11754回 古い万年筆を修理に <3>
(前回のつづき) 修理にだした万年筆は、意外に高くついた。私は店頭で簡単に調整できると思っていたのだが、工場へ送って修理するという。 2本の修理代は、その万年筆1本が買えるくらいのものだった。…
-

連載11753回 古い万年筆を修理に <2>
(前回のつづき) 万年筆には古い思い出があって、ときどき記憶がよみがえってくることがある。 敗戦後の北朝鮮の平壌に私たちの一家がいたときの話だ。 状況の激変に私たちがなすすべもなく呆然とし…
-

連載11752回 古い万年筆を修理に <1>
先日、長年使っていた万年筆の調子が悪くなってきたので、丸善の文房具売場へもっていって修理してもらった。 この何十年かずっと2本の万年筆を使って原稿を書いてきた。特に高価でもない国産の万年筆である…
-

連載11751回 ズボンに歴史あり <4>
(前回のつづき) ズボンという。トラウザスという。パンツという。スラックスという。それぞれ違った言葉だろうが、要はズボンだ。 そもそもズボンという言葉はどこからきたのだろうか。敵性言語が禁止さ…
-

連載11750回 ズボンに歴史あり <3>
(昨日のつづき) 再び四、五十年前のズボンをなぜ今も愛用しているかについて書く。 まず、はき心地がいいのだ。どこがどう良いかは、うまく説明できないが、とにかくはいていて気持ちがいいのである。 …
-

連載11749回 ズボンに歴史あり <2>
(昨日のつづき) きょうはNHKのスタジオで、WBCの日本チームの監督をつとめた栗山英樹さんと対談をした。 栗山さんは海千山千の強者をひきいて見事に優勝した、新しいタイプの監督である。濃紺のス…
-

連載11748回 ズボンに歴史あり <1>
つい先頃まで猛暑とか騒いでいたと思ったら、たちまちコートを着る季節になった。シワだらけの古い服を引っぱりだして、ブラシを当てて着る。 いつ頃から使っているコートだろうか。たぶん、30年以上はたっ…
-

連載11747回 口舌の徒として
毎年そうだが11月になると、なんとなく万事、あわただしい気配がただよってくる。 出版界だけでなく、どちらさんもすでに年末進行の切迫感に追われているらしい。 今週から来週にかけて、雑誌の編集者…
-

連載11746回 歌はどこへいったか <4>
(昨日のつづき) 前の大戦中、私たち国民はさまざまな歌に背中を押されて戦争遂行の意欲を燃やした。歌に励まされて、一死国に身命を捧げようと固く決意したのである。 その決意は決して一時の感情ではな…
-

連載11745回 歌はどこへいったか <3>
(昨日のつづき) いまでも歌は盛大にうたわれているじゃないか、と言う人がいる。たしかに街のあちこちにカラオケの店があり、多くの人々が声を張りあげて歌っている。 若い世代はもちろんのこと、年輩者…
-

連載11744回 歌はどこへいったか <2>
(昨日のつづき) 1952年の5月、私が上京して大学生となった頃、朝鮮戦争はまだ続いていた。休戦したのは翌年である。 5月1日に皇居前広場で<血のメーデー事件>と呼ばれる事件がおきた。日比谷通…
-

連載11743回 歌はどこへいったか <1>
私が学生の頃、というのは1950年代前半の頃のことだ。 大学の構内でも、その他の場所でも、仲間が3人集ると、よく歌をうたったものだった。 当時は「うたごえ運動」というものが流行して、歌をうた…