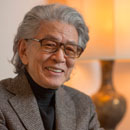五木寛之 流されゆく日々
-

連載11720回 言葉は時代とともに <1>
先ごろ、毎日新聞を読んでいて妙に面白く感じた記事があった。 2022年に文化庁がおこなった世論調査の話である。その調査のなかに<国語に関する調査>というのがあったらしい。 調査というと、なん…
-

連載11719回 雑誌「面白半分」の臨終 <5>
(昨日のつづき) このコラムの連載を読んで、 「リトルマガジンは今でも沢山でてるんじゃないですか」 と、ある編集者に言われた。 たしかにメジャーではないユニークな小雑誌は、沢山でている。…
-

連載11718回 雑誌「面白半分」の臨終 <4>
(昨日のつづき) 『面白半分』の終刊号の「編集後記」は、冗談半分のなかにも無念さがにじんでいて、いま読むと感慨がわいてくる。 編集スタッフの筆頭、阿奈井文彦さん。 <★故『面白半分』誌、葬儀に…
-

連載11717回 雑誌「面白半分」の臨終 <3>
(昨日のつづき) 『面白半分』の最終号(臨終号)に、田辺聖子さんが<腰巻大賞>のことを書いている。 <腰巻大賞>とは、私が編集長時代に創設した本のオビを対象とするフザケた賞だ。 この賞の第2回…
-

連載11716回 雑誌「面白半分」の臨終 <2>
(昨日のつづき) 創刊号というのはおおむねそうだが、背延びしてきわめて豪華である。 初代編集長の吉行淳之介さんの顔もあってか、巻頭のエッセイ欄も、大岡昇平にはじまり、しんがりの開高健までなかな…
-

連載11715回 雑誌「面白半分」の臨終 <1>
かつて、リトルマガジンの時代というものがあった。有力出版社が大量に発行する雑誌ではなく、どこからともなくボウフラのように湧いてきた小雑誌が幅をきかせた時代だ。 そんな風潮のなかで、かなり目立った…
-

連載11714回 健康法ならぬ養生 <5>
(昨日のつづき) 40代から50代にかけて、私の持病だった片頭痛(以前は偏頭痛と書いていた)を、どのようにして切り抜けたかは、これまで繰り返し書いてきた。 たぶん最近の読者は御存知ないと思うの…
-

連載11713回 健康法ならぬ養生 <4>
(昨日のつづき) 体がひそかに発する信号を、<身体語>という。私が勝手に作った言葉だ。 体調になにか異変があるとき、事前に体がひそかな信号を発する。それが身体語だ。いうなれば予感のようなもので…
-

連載11712回 健康法ならぬ養生 <3>
(昨日のつづき) この雑文のタイトルに『健康法ならぬ養生』という言葉を選んだのには、理由がある。 <健康法>というのは、病気を否定する発想だろう。健康と不健康を峻別して、病気を悪と考え、健康を善…
-

連載11711回 健康法ならぬ養生 <2>
(昨日のつづき) 私は少年時代から自分の体のことに少なからず関心を抱いてきた。 母を早く亡くし、さらに父親も療養中だったこともあるだろう。 しかし、大学生時代は、健康なんぞにかまっている余…
-

連載11710回 健康法ならぬ養生<1>
健康、という言葉がなぜか好きではない。 五体健全がイヤなのではなくて、健康という心身の状態に不信を抱いているのだ。 そもそも、なにをもって健康というのだろう。検査の結果、いろんな数値が安全枠…
-

連載11709回 記憶の地下茎より <4>
(昨日のつづき) その村の名前が、どうしても思い出せない。 私の最初の記憶の舞台になった小さな村である。 いまは韓国のどこかの地方の町だろうが、当時は韓国という言葉は使われていなかった。す…
-

連載11708回 記憶の地下茎より <3>
(昨日のつづき) 産湯を使ったときの記憶が残っているという人がいる。生まれたときに取り上げてくれた女の人の顔をおぼえているという作家の文章を読んだこともあった。 そんな事が実際にあるのだろうか…
-

連載11707回 記憶の地下茎より <2>
(昨日のつづき) 母親についての記憶があまりないのはどういうわけだろう。 一つは彼女が職業婦人だったことかもしれない。 福岡の女子師範学校をでて、地方の小学校の教師として働き、そこで同じ小…
-

連載11706回 記憶の地下茎より <1>
憶えているはずの人の名前が、なぜか出てこない。 あれほど何度も文章に書き、手紙ももらった相手であるにもかかわらず思い出せないのだ。認知症の初期の症状かもしれない。 そういう事が昔からしばしば…
-

連載11705回 坊主頭の夏がゆく <5>
(昨日のつづき) 昔は子供のことを<坊主>といった。 <ヤンチャ坊主>とか、「この小坊主」などといったものである。 これは、いわゆる<お坊さん/僧侶>のことではない。たぶん髪の毛を丸刈りにし…
-

連載11704回 坊主頭の夏がゆく <4>
(昨日のつづき) 昨夜、朝方まで新人賞の原稿を読んでいたので、疲れた。 長篇小説3本となると、とても一晩で読み終えるのは難しい。まして新人賞の候補作とあっては、速読というわけにもいかず、結局、…
-

連載11703回 坊主頭の夏がゆく <3>
(昨日のつづき) 私が小学校に入学したのは、たぶん昭和10年代のはじめの頃だろう。中学1年のときに敗戦の夏を迎えたのだから、昭和12、13年あたりではあるまいか。 その時の写真を見ると、当時お…
-

連載11702回 坊主頭の夏がゆく <2>
(昨日のつづき) 朝、起きてトイレに行き、洗面所にいく。 鏡を見て、一瞬、戸惑った。鏡の中に見知らぬ男が映っていたからだ。坊主頭で、すこぶる人相が悪い。 ギョッとして身構えたが、すぐにそれ…
-

連載11701回 坊主頭の夏がゆく <1>
仏門に入って頭を丸めることを<剃髪>という。いわゆる坊主頭だ。 一般には戒師が出家する者に戒をあたえて、髪を剃るのだが、真宗などでは在家の者の頭にカミソリを当て、剃髪に擬して儀式をおこなうらしい…