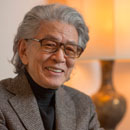五木寛之 流されゆく日々
-

連載10086回 見えない時代の現実 <3>
(昨日のつづき) かつてこの国は鎖国ということをした。だが実際には、さまざまな抜け道のあったことが、最近の研究では明きらかにされている。 そしていま、私たちはグローバル化の波の中で翻弄されてい…
-

連載10085回 見えない時代の現実 <2>
(昨日のつづき) 例の無人攻撃機、ドローンが気になってしかたがない。先日のニュースでは、米軍だけでなく、CIAもドローンを使っているらしい。暗殺というとおどろおどろしいが、消去といえばなんとなく軽…
-

連載10084回 見えない時代の現実 <1>
この何十年か、私が歩きまわる街の一角になんとなく気になる変化がおきてきた。 以前はあちこちに顔なじみのホームレスの人たちがいたのである。公園のベンチに、歩道橋の下に、ビルの入口の階段に、何人もの…
-

連載10083回 陰謀論というけれど <4>
(昨日のつづき) 歴史は経済で動いている、という見方がある。また最近では、宗教が歴史の流れを作る、という説もある。 それらの立場は、いずれも理論的だ。しかし、人間の世界は、はたして理論どおりに…
-

連載10082回 陰謀論というけれど <3>
(昨日のつづき) 第1次世界大戦に日本が参戦したのは、1914年8月である。大正3年のことだ。参戦といっても、青島を占領したことと、ドイツ領南洋諸島を支配したぐらいで、大した参加ではない。しかし、…
-

連載10081回 陰謀論というけれど <2>
(昨日のつづき) 「要するに陰謀論にすぎない」 とか、 「そいつは陰謀論みたいなもんだな」 とか、 「一種の陰謀論である」 とか、そういう言い方をよく耳にする。要するに裏づけのない空…
-

連載10080回 「陰謀論とはいうけれど」 <1>
妙に着物姿の若い娘たちが多いと思ったら、どうやら今日は「成人の日」であるらしい。あい変らず白いショール? を肩にかけた姿は、なんとなく時代とズレた感じがする。 成人ということは、一体どういうメリ…
-

連載10079回 明日は誰にも判らない <3>
(昨日のつづき) 人はだれでも「気持ちのいい話」をききたがるものである。 しかし「気持ちのいい話」というのは、どこかで事実が編集されているものだ。高級な寿司屋でいろんな材料を惜しげもなく切って…
-

連載10078回 明日は誰にも判らない <2>
(昨日のつづき) 「気持ちのいい話」「心が洗われるような話」というものがある。いわゆる美談というやつだ。美談というと、どこか道徳的、修身的な感じがする。そうでなくて、人間っていいな、とか、日本人も大…
-

連載10077回 明日は誰にも判らない <1>
正月3日間は、ベッドの中で過ごした。枕元に山ほど本を積んで、一冊ずつその山を崩して日を送った。まさに寝正月である。 集中的に読んだのは、「シベリア出兵」に関しての資料が中心だった。 「シベリア…
-

連載10076回 今年嬉しかったこと <3>
(昨日のつづき) きょうはインターヴュー、3つ。 取材の場所にのぞむ前は、できるだけ言葉ずくなに、慎重に答えようと心に誓う。 ところが、インターヴューが始まると、いつのまにか本音を勝手にし…
-

連載10075回 今年嬉しかったこと <2>
(昨日のつづき) 困ったことは沢山ある。それに大変だったことも結構あった一年だった。しかし、嬉しかったことを探すとなると、これがなかなかむずかしい。 前回、4つまでは挙げることができた。さて、…
-

連載10074回 今年嬉しかったこと <1>
(昨日のつづき) 今年は大変な一年だった。 世界も、そして私自身にとってもである。 とはいえ、これまで大変でなかった年などあっただろうか。 生まれて八十余年、世界も、この国も、私自身も…
-

連載10073回 師走の街に風が吹く <4>
(昨日のつづき) 外交面でも、内政面でも、どうもパッとしない今年の暮れだが、嬉しいニュースが一つ。 先日来、さんざん苦労して編集部が作成していた『流されゆく日々』の〈1万回記念全タイトル一覧リ…
-

連載10072回 師走の街に風が吹く <3>
(昨日のつづき) いよいよ今年もおわりに近づいた。 ストックなしの当日本番というスタイルで、よくもこれまで無事故でこられたものである。 夏の終りに1万回に達したとき、一応、この辺で打ち止め…
-

連載10071回 師走の街に風が吹く <2>
(昨日のつづき) 景気がいいのか、悪いのか。 勤労者の実質賃金は、低下し続けているという。世帯当りの貯金を、とり崩して暮らしていると統計には出ている。 しかし、街の眺めはミニバブルだ。 …
-

連載10070回 師走の街に風が吹く <1>
先週あたりから街の気配が妙にざわついている。師走とは、よく言ったものだ。横断歩道を渡る人の波も、心なしか前のめりになっている感じ。 「忘年会のピークは、先週末あたりでしたね」 と、タクシーのド…
-

連載10069回 今週読んだ本の中から <10>
(昨日のつづき) 今週も終りである。読んだ本の中から、アトランダムに書名をあげておくことにしよう。どれも印象に残った本ばかりだ。活字を読むということは、本当におもしろい。このことだけでも、人生の目…
-

連載10068回 今週読んだ本の中から <9>
(昨日のつづき) フォーク・クルセダーズの結成から、メディアへのデビュー、そして解散と再びの出会いなど、一つの戦後史としても貴重な資料が、『コブのない駱駝』の一冊にはぎっしりつまっていて、巻をおく…
-

連載10067回 今週読んだ本の中から <8>
(昨日のつづき) 『コブのない駱駝』(岩波書店)は、〈きたやまおさむ「心」の軌跡〉という副題がそえられている。「序」に当る部分には〈北山修による、きたやまおさむの「心」の分析〉というサブタイトルもあ…