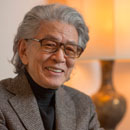五木寛之 流されゆく日々
-

連載10412回 ヘルス・リテラシー <1>
最近の健康情報の氾濫は、すさまじいの一語につきる。テレビ、週刊誌をはじめ、新聞、単行本など、かつてなかったほどの健康特集のフィーバーぶりである。 これまでも健康や病気に関する記事は、メディアの米…
-

連載10411回 下山の成熟とはなにか <5>
(昨日のつづき) 欧米にコンプレックスを持つわけではないが、ヨーロッパやアメリカの街を歩いて感じることがある。 それはとりもなおさず時間をかけて熟成した文明の厚味である。 わが国にも歴史を…
-

連載10410回 下山の成熟とは何か <4>
(昨日のつづき) たかが一つのバッグである。どんな名前をつけようが、それはメーカーの勝手だ。しかし、カラッチオラの名前を冠したバッグには、背後に一つの物語がある。 その物語のイメージが文明の成…
-

連載10409回 下山の成熟とは何か <3>
(昨日のつづき) なぜ私はそのドイツ製のバッグを購入したのか。カラッチオラという商品名は、いかなる人物の物語から名づけられたのか。 私はくわしいことは知らないが、ルドルフ・カラッチオラという人…
-

連載10408回 下山の成熟とは何か <2>
(昨日のつづき) 成熟とはどういうことか。 それは経済力の発展とイコールではない。ある意味で、成熟とは「物語」の有無ではないかと思う。 一つの商品を輸出する。それを外国の人びとが買う。そこ…
-

連載10407回 下山の成熟とは何か <1>
かなり以前、幻冬舎から『下山の思想』という新書を上梓したことがあった。 高成長の時代、すなわち登攀の時代は終った。これからは下山の時代である。私たちは下山の思想を強化しなければならない、といった…
-

連載10406回 老いと死を見つめて <5>
(昨日のつづき) さて、<孤独に耐え切ることは人間には不可能であり、そして不可能と知りつつも人間は、昇華の手段を希求するのである>と西部氏は言う。 <さらにそのあとにかならずやってくる死の恐怖、…
-

連載10405回 老いと死を見つめて <4>
(昨日のつづき) 高齢者の老いについて、西部邁の文章はこんなふうに続く。 <(前略)私も二十代の前半において、三年ばかり、結構な孤独を味わったことがあるが、それは自分であえて創りだした孤独の環境…
-

連載10404回 老いと死を見つめて <3>
(昨日のつづき) 「老い」というものは、たしかに厄介で困ったものだ。私も日々、それを痛感しながら生きている。 訪れてくる人も少くなり、語り合うべき友人は次々と逝ってしまう。記憶力や表現力もおとろ…
-

連載10403回 老いと死を見つめて <2>
(昨日のつづき) 『愛と死をみつめて』という物語や歌が大流行したのは、1964年の東京オリンピックの頃ではなかったか。本、映画、TVドラマ、そして青山和子のうたう「まこ 甘えてばかりでごめんね」とい…
-

連載10402回 老いと死をみつめて <1>
西部邁『自死について』(富岡幸一郎編著/アーツアンドクラフツ刊)を読むと、この著者がずいぶん早くから「死」について考えていたことがわかる。生涯に共著を含めて200冊をこえるという著者の仕事のなかから…
-

連載10401回 物価の変動いま昔
私が九州の田舎から上京したのは、昭和27年の春だった。1952年のことである。 当時は福岡から東京まで、特急列車で24時間かかった。 大学の授業料が1万7000円だった。入学金が5万円。 …
-

連載10400回 『群論』という考え方 <5>
(昨日のつづき) ちかぢか刊行予定の本の打合せにやってきた女性編集者が、 「ゲンロンカフェに出られたんですってね。前もって判ってたら絶対いってたのに」 と、残念そうに言う。 一緒にきてい…
-

連載10399回 『群論』という考え方 <4>
(昨日のつづき) 『ゲンロンカフェ』は、五反田にある。本郷や新宿でないところがいい。残念ながら風俗街のどまん中ではなく、南口の蔦屋書店の脇をちょいとはいったあたりだ。 会場にはいって、すぐに60…
-

連載10398回 『群論』という考え方 <3>
(昨日のつづき) 15世紀、蓮如という怪物が登場する。宗門では絶大な権威をもち、一般にはすこぶる評判の悪い宗教家である。 かつて私が『蓮如』という連載を中央公論で始めたときには、驚き呆れる人が…
-

連載10397回 『群論』という考え方 <2>
(昨日のつづき) 渋谷のジァン・ジァンを皮切りに、いろんなところで『論楽会』をやった。 沖縄の古謝美佐子がうたう『童神』というオリジナル曲も、その中で生れた歌の一つである。「論」と「楽」のコラ…
-

連載10396回 『群論』という考え方 <1>
昔、そう、あれは何十年か前のことだった。フリーのライターたちが集って、共立講堂で言論集会をやるから出ろと言う。 その会の名前が、ナントカ講演会とかいうタイトルだったので、首をかしげたことがある。…
-

連載10395回 日々これ雑事に過ぎて <5>
(昨日のつづき) 神隠しというものは本当にあるものだ。もっとも消えるのは人間ではない。モノである。 ついさっきまで手に持っていたモノが消えている。どこかに置いたらしいのだが、いくら身のまわりを…
-

連載10394回 日々これ雑事に過ぎて <4>
(昨日のつづき) 最近、というか近年、健康に関する記事や特集を新聞・雑誌でしばしば見うけるようになった。 以前からジャーナリズムは、健康を一つのテーマのように扱っていたものである。飲尿療法とか…
-

連載10393回 日々これ雑事に過ぎて <3>
(昨日のつづき) 夕方から雨。先週から冬の服を仕舞って、薄着をしていたのだが、寒いのでツイードのジャケットを着る。 金沢市から文化政策課長の新保氏ほかのスタッフが訪れてきて、次回の泉鏡花文学賞…