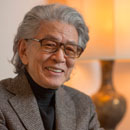五木寛之 流されゆく日々
-

連載10216回 風邪は万病の元か <4>
(昨日のつづき) 鼻水が垂れはじめて今日で1週間目である。熱もさがったし、咳もおさまったのだが、いまひとつすっきりしない。やはり風邪のコントロールに失敗したらしい。 失敗といっても、対応を怠け…
-

連載10215回 風邪は万病の元か <3>
(昨日のつづき) 先週からの風邪が、まだ抜けない。熱は下がったものの、痰が喉にからんでゴホン、ゴホンと咳が出る。 どうやら短期風邪パス作戦は失敗したかのようだ。1週間も続く風邪は、悪い風邪にき…
-

連載10214回 風邪は万病の元か <2>
(昨日のつづき) あの親鸞でさえも、<ちょっと具合いが悪いと、このまま死ぬのではないかと不安だ>と言っている。 体調が悪くても、若いあいだはそれほど気にならないものだ。まだまだ先がある、と思い…
-

連載10213回 風邪は万病の元か <1>
ひどい風邪を引いてしまった。喉風邪とでもいうのだろうか。声がガラガラになって、喉が痛む。咳がでる。念のために体温を計ってみたら38度5分以上ある。体がだるい。 数日前から喉の調子が変だった。それ…
-

連載10212回 デラシネの世紀とは <9>
(昨日のつづき) 定住者と移動者を、かつて私は内臓と血液にたとえたことがある。この国もかつては流動する人びとが各地を漂流して、列島を活性化していた。「まれびと」がそうであり、遊芸の徒がそうであり、…
-

連載10211回 デラシネの世紀とは<8>
(昨日のつづき) 私が思うところでは、現代のデラシネとは難民のことである。かつてジプシーと賤称された流浪の民だけがデラシネではない。世界はデラシネの坩堝である。U・S・Aに送られたアフリカ系アメリ…
-

連載10210回 デラシネの世紀とは <7>
(昨日のつづき) 筑豊は近代日本のエネルギー源として北九州の一角に築かれた炭鉱地帯である。そこはかつて豊後百姓と呼ばれた農民たちの平和な田園地帯だった。明治以後、財閥や玄洋社などの開発によって巨大…
-

連載10209回 デラシネの世紀とは <6>
(前週のつづき) 歴史をふり返ってみると、強制移住者、追放者、移民、引揚者、亡命者などの存在が無数に浮かびあがってくる。生活苦のために故国を捨てた人びとが新大陸をめざす。その地の先住民たちが追われ…
-

連載10208回 デラシネの世紀とは <5>
(昨日のつづき) 私が『デラシネの旗』を別冊文芸春秋に発表したのは、1968年(昭43)の10月だった。単行本として刊行されたのは翌年の秋である。 その頃、私は熱にうかされたようにスペイン戦争…
-

連載10207回 デラシネの世紀とは <4>
(昨日のつづき) モーリス・バレスの活躍したのは、第1次世界大戦の頃だろう。国民の栄光をうたいあげ、当時は<青年たちのプリンス>と称された存在だったらしい。ナショナリズムを鼓吹し、時代の寵児として…
-

連載10206回 デラシネの世紀とは <3>
(昨日のつづき) ナショナリズムというのは、地下のマグマに似ている。地表に噴出する現象がおさまっても、それは一時的なものだ。地下ふかくに脈動して絶えることがない。そして周期的に噴火する状況をうかが…
-

連載10205回 デラシネの世紀とは <2>
(昨日のつづき) どこで見た映像だったか。 あっというまに過去の事になってしまった感のあるパリのテロ事件の後日談である。ムハンマドを戯画化したことで、ある雑誌社の編集部がテロの被害にあった。そ…
-

連載10204回 デラシネの世紀とは <1>
これまで50年あまりの作家生活のなかで、ずいぶん雑多な小説を書いてきた。自分でも呆れるほどの統一感の無さである。しかし、私自身そのことを負い目には感じてはいない。「雑であること」と「同時代的であるこ…
-

連載10202回 今日は昨日の風が吹く <4>
(昨日のつづき) 今夕の日刊ゲンダイをめくっていたら、『流されゆく日々』のコラムと同じ面に宮内勝典さんの<著者インタビュー>が出ていた。『永遠の道は曲りくねる』という大長篇で、河出の『文芸』に連載…
-

連載10201回 今日は昨日の風が吹く <3>
(昨日のつづき) サイモン・コンウェイの『スパイの忠義』(ALOYALSPY/熊谷千寿訳/ハヤカワ文庫)を読んでいたら、ロンドンという街についてこんな事が書いてあった。登場人物の会話の中にでてくる…
-

連載10200回 今日は昨日の風が吹く <2>
(昨日のつづき) 今夜のテレビ報道番組は、どの局も都議会議員選挙のニュースで花盛りである。 キャスターやゲスト・コメンテイターの発言も、ほとんど横並びといった感じ。 「ファースト優勢とは予想…
-

連載10199回 今日は昨日の風が吹く <1>
日曜日は、私にとって<地獄の日曜日>である。連載の〆切りが3本重なって、眠る時間がない一日だ。 おまけに今回は都議会議員の選挙とあって、どうしてもテレビを視てしまう。 現在、都民ファーストが…
-

連載10198回 インフレかデフレか <5>
(昨日のつづき) 「インフレになる」ことを「景気が良くなる」と同一視するのはどうか。 インフレで活気づくのは商売である。小さな店から大企業まで、インフレは好景気の代名詞だ。 きのう10円で売…
-

連載10197回 インフレかデフレか <4>
(昨日のつづき) 私は経済学どころか、経済そのものについても全くの無智の輩である。 しかし経済の理論は知らなくても、日々、金銭とモノとを消費しながら生きている。その立場から自分の実感を語ってい…
-

連載10196回 インフレかデフレか <3>
(昨日のつづき) 私がタクシーというものに戦後はじめて乗ったのは、1950年代か60年代のはじめ頃だった。ゲルピンの身だったが、友人が急病になって病院へ運んだのである。 タクシー代は、大事にし…