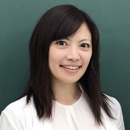時間栄養学的「気になる食品」
-

【湯葉】大豆を凝縮した良質な植物性タンパク質源が 悪玉コレステロールを下げる
湯葉は、温めた豆乳の表面に形成される薄い膜をすくい上げて作られる食品で、豆腐と同様に大豆と水のみを原料としています。その起源は中国の精進料理で、禅宗文化とともに日本へ伝わったそうです。日本では室町時…
-

【サンザシ】油物の消化をサポートして重い胃腸をすっきりさせる
サンザシは、赤く小さな実がかわいらしい果物で、中国では1000年以上前から「脂っこい食事のあとに良い実」として親しまれてきたそうです。唐代の本草書にも記載があります。肉料理が多い時代に重たくなった胃…
-

【ショートケーキ】エビデンスに基づいた健康的な食べ方
クリスマスが近づくと、街のケーキ店に並ぶ真っ赤なイチゴのショートケーキは心を華やかにしてくれますね。日本ではクリスマスの定番として親しまれていますが、大正時代にアメリカのストロベリーショートケーキを…
-

【ブロッコリースプラウト】脳や腸を整え睡眠の改善も期待できる
ブロッコリーの新芽を育てたブロッコリースプラウトは、発芽から数日ほどの柔らかい芽の段階で収穫されます。 日本では比較的新しい食材の印象がありますが、じつは発芽野菜の利用そのものは古く、東アジ…
-

【黒豆】老化予防だけでなく運動後の筋ダメージも抑える
おせち料理で「まめに働く」「まめに暮らす」という語呂とともに、健康と勤勉を象徴する食べ物として大切にされてきた黒豆。奈良時代の文献にも登場し、平安期の貴族の食卓や寺院の精進料理でも利用されるなど、長…
-

【高野豆腐】精進料理の代名詞…なぜフレイル予防食材として人気なのか?
豆腐を凍結・乾燥させて保存性を高めた、日本独自の伝統的な加工食品である高野豆腐。起源にはいくつかの説がありますが、高野山の厳しい冬に豆腐が自然に凍結し、その後、乾燥したことで保存が利く食品として利用…
-

【もち麦】血糖値と腸内環境の改善で再評価…ごはんやスープに混ぜて食べたい
日本では弥生時代の遺跡からも出土している大麦は、古くから米と並ぶ主食作物でした。特に江戸時代には、夏場の体調不良を防ぐ「麦飯」が奨励されていたので、武士から庶民まで広く食されていた記録があります。た…
-

【パクチー】血糖や脂質の改善を期待して夕食に食べたい
パクチーは独特の香りで好みが分かれますが、古くから世界各地で利用されてきたハーブのひとつです。セリ科の一年草で、学名はコリアンドラム・サティバム。 原産地は地中海東部から中東とされ、約300…
-

【空芯菜】夜に食べて安眠の助けにしたい…疲れがたまったときに役立つ
空芯菜は、茎の内部が空洞になっていることからこの名で呼ばれる東南アジア原産の葉物野菜です。暑い地域でよく育つため、日本では夏場に多く出回りますが、近年は通年で入手できる店も増え、中華料理などで口にさ…
-

【長ねぎ】豚肉と一緒に摂ると疲労回復や集中力維持に効果的
長ねぎは、古くから日本人の食卓に欠かせない香味野菜のひとつです。その歴史は奈良時代に中国から伝わったとされます。平安時代の文献「延喜式」にも「葱(ねぎ)」の記載があり、当時から食卓にのぼっていたこと…
-

【めかぶ】朝食の「めかぶファースト」は腸内環境を改善し血糖値を抑える
めかぶは、ワカメの根元部分にあたる「芽株」を食用にしたもので、古くから日本の食卓で親しまれてきました。平安時代の文献にも海藻を食べていた記録があり、保存のために干したり、刻んで酢で和えたりするなど、…
-

【黒ニンニク】ポリフェノールが生の数倍!抗酸化能がスゴイ
ニンニクを一定の温度と湿度で長期間熟成発酵させると、色が黒く変わり「黒ニンニク」になります。かなり見た目の色も風味も変化するのですが、これは熟成中に糖とアミノ酸の化学反応(メイラード反応)が起きるか…
-

【生ハム】昼間に少量食べるのが正解…夜は塩分排泄能力が低下
生ハムは、古代ローマ時代から続く伝統的な保存食。地中海沿岸で塩漬けと乾燥による保存技術が発展し、中世には修道院や貴族の館で貯蔵食として重宝されてきました。 現在ではスペインの「ハモン・セラー…
-

【むかご】塩分排出を助けて血圧を安定させる…昼に食べたい
むかごは、ヤマノイモやナガイモのつるの葉腋にできる直径1~2センチほどの小さな球状の芋で、親芋と同じ遺伝子を持つ「栄養繁殖体」にあたります。 秋になると自然にぽろりと落ちる姿から、古くから「…
-

【スンドゥブ】「セカンドミール効果」に期待して昼に食べたい
スンドゥブ(純豆腐チゲ)は、押し固めないやわらかな純豆腐を主役にした韓国の鍋料理で、朝鮮王朝時代の記録に原型が見られます。近代以降は魚介や唐辛子を合わせる大衆料理として定着しており、日本でもメジャー…
-

【蒸し豆】食物繊維が豊富…血糖上昇が気になる夕方に食べたい
豆は人類最古の栽培植物のひとつであり、紀元前1万年以上前の遺跡からレンズ豆やひよこ豆の利用が確認されています。日本でも縄文時代の遺跡からアズキやエンドウが出土していて、古来人々の主食・副食を支えてき…
-

【コチュジャン】3カ月でお腹周りがスリムに!朝に取りたい発酵調味料
コチュジャンは韓国を代表する伝統的な発酵調味料で、その名は唐辛子を意味する「コチュ」と、味噌や醤を意味する「ジャン」に由来しています。唐辛子粉、もち米、大豆発酵粉、塩を混ぜて甕(ジャンドク)に仕込み…
-

【モッツァレラチーズ】筋肉作りなら朝、骨の健康なら夜に食べたい
モッツァレラチーズは、イタリア南部カンパニア州を発祥とするフレッシュチーズで、その名は「mozzare=切る」に由来しています。湯の中で練った「カード」(発酵させたミルクを凝固させた塊)を手でちぎる…
-

【マスカット】血圧改善や免疫維持に役立つ…朝昼に食べたい
マスカットの歴史は古く、古代エジプトの壁画にブドウ栽培が描かれていたり、ギリシャ・ローマ時代には貴族の食卓を飾る高級果実として珍重されていたようです。宴席を華やかにするだけでなく、宗教儀式の供物にも…
-

【カダイフ】組み合わせがカギ…果物と合わせて夜に食べたい
「カダイフ」という不思議な名前の食材が、日本でも注目を集めています。専用の器具を使って生地を極細に垂らしながら糸のように焼き上げたものですが、その姿はまるで「天使の髪」とも称されるほど美しく、見た目の…