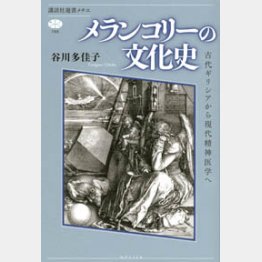「メランコリーの文化史」谷川多佳子著
外出自粛や会社の倒産などコロナ禍に起因する〈コロナうつ〉が大きな問題となっている。うつ=メランコリーは、古来さまざまな表象をもって描かれてきた。有名なのは本書のカバーにも使われているアルブレヒト・デューラーの銅版画「メレンコリアⅠ」だろう。翼をもつ若い女性と子供。女性はコンパスを手に持ち、足元には、かんな、定規などが配され、背後の壁には天秤、鐘、砂時計、魔方陣などが掛けられている。なにより、座って肘をつき左手を頬に当てる女性のポーズは、ロダンの「考える人」や夏目漱石のよく知られる写真など、メランコリーを表す典型的な姿勢だ。
本書は、古代から現代まで、メランコリーがどのように語られ、形象されてきたかの系譜をたどりながら、宗教や医学ほか、さまざまな分野にどんな影響を及ぼしてきたかを通覧している。
メランコリーの語源は「黒い胆汁」を意味するギリシャ語。これは古代ギリシャにおいて、人間は血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁の四体液から作られているという考えからきており、体の不調はこれら4つの体液のバランスが崩れたときに起こるとされていた。そしてそのいずれが多いかによってその人の性格分類もされ、黒胆汁質=憂うつ質と同定されていたのだ。
この四体液説は以後も引き継がれ、そこに中世の占星術などが融合され、そうして出来上がったのがデューラーの絵ということになる。四体液説から完全に脱するのは精神医学が登場する19世紀以降になってからで、シャルコー、フロイトなどの精神医学者の登場によって、現代的なメランコリーの概念が定着することになる。
アリストテレスはメランコリーを天才の証しと評価し、現代の精神医学でも「創造の病」という考え方がある。いずれにしてもメランコリーは単なる病気ではなく、己を内省する大きな働きでもあることが、本書を通じてよく見えてくる。 <狸>
(講談社 1760円)