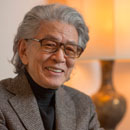五木寛之 流されゆく日々
-

連載11324回 生命の格差について <2>
(昨日のつづき) 経済的な格差について論じられるのは、古く万葉の時代からである。生命の格差に関してもそうだ。 わが国には奴隷はいなかったと言われているが、言葉の違いだけで、奴隷以下の存在は少く…
-

連載11323回 生命の格差について <1>
先月から今月にかけて新刊を3冊出した。そのため、取材やらパブリシティーで連日スケジュールがつまって大変である。 コロナ渋滞の折から、あまり人前に出たくないのだが、仕事だから仕方がない。出版は時代…
-

連載11322回 現代の「悪」とは何か <4>
(昨日のつづき) 法然、親鸞が山を降りて市井に身をおいた時代、世の中は少数の「善人」と大多数の「悪人」に分かれていた。そのほかに「非人」と呼ばれる人々もいた。「非人」は人外の者であるから「悪人」の…
-

連載11321回 現代の「悪」とは何か <3>
(昨日のつづき) 悪、という文字には、どこかにどす黒い陰鬱な感じがする。悪人、という言葉にしてもそうだ。 しかし、現代社会のシステムがはらむ悪のイメージは、プラスチックのように透明で軽い。そこ…
-

連載11320回 現代の「悪」とは何か <2>
(昨日のつづき) 先ごろ新聞を読んでいて、すこぶるショッキングな記事に出会った。(2―13/朝日) そもそも私は新聞の大きな記事は読まない。紙面の片隅に小さく扱かわれているような記事を拾い読み…
-

連載11319回 現代の「悪」とは何か <1>
「悪人正機」 という有名な言葉がある。12世紀~13世紀の仏教者、親鸞の説である。 それまでの仏教は個人の問題よりも、国家と朝廷の安穏を願うものだった。いわゆる「国家鎮護」の宗教だ。 それ…
-

連載11318回 「大新聞」と「小新聞」の時代
先週、このコラムで漱石の漢詩について書いたら、 「日刊ゲンダイなんかで夏目漱石のことを論じるのは、お門違いだろう」 と、ある人に言われた。 「どうして? 漱石に失礼だってことかい」 「いや…
-

連載11317回 先週読んだ本の中から <4>
(昨日のつづき) 漱石と子規との交遊は、明治22年頃にはじまったらしい。漱石、夏目金之助は第一高等中学校で英文学を専攻する学生だった。 英文学を専攻しながらも、彼は「余は少時好んで漢籍を学びた…
-

連載11316回 先週読んだ本の中から <3>
(昨日のつづき) 詩といえば読むもの、というのが最近の常識だが、もともと詩は吟ずるもの、歌うものである。声に出して、メロディーをつけてうたうのだ。 仏教のほうでは、ブッダの言葉にリズムをつけて…
-

連載11315回 先週読んだ本の中から <2>
(昨日のつづき) さて、『夏目漱石漢詩考』という本のことだが、どうも取っつきにくい本相をしていて、長いあいだ部屋の片隅に転がっていた一冊だ。本相というのは、人相に対する本の外見である。 そもそ…
-

連載11314回 先週読んだ本の中から <1>
多少、勢いは落ちてきたとはいえ、新型コロナの粘り腰は相当なものである。 このところ子供と高齢者の感染が目立ってきたようだ。この歳でコロナになれば、私なんぞはイチコロだろう。 命令されてステイ…
-

連載11313回 リモート選考会始末記 <5>
(昨日のつづき) コロナの蔓延とともに、いろんな変化が出版界にもあった。 その一つが、出版物の企画・編集という作業である。 これまで編集者の仕事といえば、書き手・作家との個人的な濃厚接触が…
-

連載11312回 リモート選考会始末記 <4>
(昨日のつづき) 机の上におかれた映像画面は、意外に鮮明で、声もクリアだし違和感がない。 丹羽編集長のリードで、各選者が順番に候補作への感想をのべていく。 ひと通り12篇の批評が終ったあと…
-

連載11311回 リモート選考会始末記 <3>
(昨日のつづき) 明日のこの原稿を書いている途中に、石原慎太郎氏の訃報がとびこんできた。 一瞬、呆然となる。 最近、<短編全集>なども出していて、がんばって仕事をやってるな、と思っていたと…
-

連載11310回 リモート選考会始末記 <2>
(昨日のつづき) この<九州芸術祭文学賞>というのは1970年(昭45)に創設され、今回で52回を迎える文学賞である。 私は第1回からずっと皆勤で出席しているのだが、最初の頃の選考委員は5名だ…
-

連載11309回 リモート選考会始末記 <1>
このところコロナのせいで、やたらとリモートが重宝されている。 テレビのゲストなども、リモート出演が多く、時にはうんざりさせられることも少くない。 画像が悪く、音質も不安定で聴きづらいからであ…
-

連載11308回 耳学問のすすめ <5>
(昨日のつづき) そもそも仏教はどのように広まっていったのだろうか。 ここで再びゴータマさんの話にもどる。ブッダは生涯をかけて何をした人なのか。 まず話をした。それを説法というか、講話とい…
-

連載11307回 耳学問のすすめ <4>
(昨日のつづき) 親鸞が浄土真宗の始祖なら、蓮如は中興の祖とされる存在だ。 蓮如という人物は、やたらと毀誉褒貶の多い人物である。要するに宗門ではとびきり重要な人物だが、外部ではひどく風当りがつ…
-

連載11306回 耳学問のすすめ <3>
(昨日のつづき) 例によって話がとぶが、ブッダという人は、一体どんなことをした人だろう。 言うまでもないが、ブッダとは、いわゆる「おシャカさま」のことだけをいう言葉ではない。一般人のレベルを超…
-

連載11305回 耳学問のすすめ <2>
(昨日のつづき) 『学問のすすめ』は、言うまでもなく福沢諭吉の話題作である。 明治5年の発行以来、巻を重ねて総数350万部に達した大ベストセラーだ。わが国における近代的、合理的な人間観を語った啓…