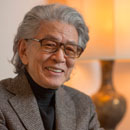五木寛之 流されゆく日々
-

連載11890回 偏見メガネの独り言 <5>
(昨日のつづき) 全国的な俳人の集りがあるから、そこで何か喋れ、といわれた時には、さすがに図々しい私も躊躇した。 俳人というのは、作家よりはるかに理論派が多い。素人の私が下手に気のきいたつもり…
-

連載11889回 偏見メガネの独り言 <4>
(昨日のつづき) 子供のころ、俳句を作ったことがある。まあ、俳句というより「俳句らしきもの」といったところだろう。 五、七、五の定型に言葉がはまっていれば大威張りといった遊びだ。 父親が日…
-

連載11888回 偏見メガネの独り言 <3>
(昨日のつづき) 6月18日の産経新聞の朝刊に、動物行動学者の竹内久美子さんが、『メスのリーダーが成り立つ条件』という文章を寄稿されていた。 私は竹内行動学の素朴なファンなので、とても興味ぶか…
-

連載11887回 偏見メガネの独り言 <2>
(昨日のつづき) きょうスーパーでミカンを買って、キャッシュで支払おうとしたら、店員さんが、 「パネルにタッチしてください」 と言う。 「いや、現金だよ」 「だから――」 と、相手が…
-

連載11886回 偏見メガネの独り言 <1>
兼好法師だか誰だったか忘れてしまったが、昔の有名なエッセイストが、こんな事を言っていた。正確な引用ではないが、おおむねこんな話である。 <事業で成功しようと思うなら、この世の中が一変することもある…
-

連載11885回 時代とズレた生き方 <5>
(昨日のつづき) 年寄りは昔ばなしをしたがるものだ。 聞かれてもいないのに、自分の若い頃の出来事や、やたら昔の人名などを持ち出したりする。 旧友同士がお互いに古い記憶を語り合うのは勝手だ。…
-

連載11884回 時代とズレた生き方 <4>
(昨日のつづき) うつりゆく時代にシンクロして生きることは、それほど難しいことではない。 人並みの運動神経がありさえすれば、誰にでもできることである。 むしろズレることのほうが、はるかに難…
-

連載11883回 時代とズレた生き方 <3>
(昨日のつづき) ときどき若い人たちと、まったく同じような服装の同年配者に会うことがある。 帽子からリュック、靴まで、今ふうというか若者の恰好だ。 それなりに似合ってはいるけれど、なんとな…
-

連載11882回 時代とズレた生き方 <2>
(昨日のつづき) 5、6年前までは、自分が時代とズレていることが気になったものだった。 意識してもしなくても、その世代的ズレは日々リアルに迫ってくる。 私が新聞や雑誌で最近ふえてきたヨコ組…
-

連載11881回 時代とズレた生き方 <1>
時代はすごい速さで変化していく。 世の中が変るのは当り前だが、最近はそのスピードがメチャクチャ速いのだ。 「そうですかねぇ」 と、若い友人が首をかしげて、 「時代が速く変化するというより…
-

連載11880回 一にケンコー、二にゲンコー <5>
(昨日のつづき) 小説雑誌はなやかなりし頃は、当時の流行作家に原稿を書かせるのは大変だった。 ホテルや社の個室に押しこめて、いわゆるカンヅメ状態にして書かせるのは定番だが、そこから抜け出してい…
-

連載11879回 一にケンコー、二にゲンコー <4>
(昨日のつづき) 私が『小説現代』の新人賞をもらって、原稿が雑誌に掲載されたのは1966年の春である。 原稿はエンピツ書きだった。 書いては消しゴムで消して書き直し、一字一字、律義な読みや…
-

連載11878回 一にケンコー、二にゲンコー <3>
(昨日のつづき) かなり以前のことになるが、通信販売で、こんな目録が送られてきたことがあった。 <有名作家の直筆原稿/書き込み、校正赤字アリ。状態良好、価格○○○円。希少価値> そして生原稿…
-

連載11877回 一にケンコー、二にゲンコー <2>
(昨日のつづき) <一にケンコー、二にゲンコー> とは、作家として期待されながら、病に倒れたIさんが葉書に書いて送ってくれたフレーズである。 病床からの便りだっただけに、切実感があった。 …
-

連載11876回 一にケンコー、二にゲンコー <1>
半世紀あまり、<日刊ゲンダイ>の読者兼筆者としてすごしてきた。 最近のゲンダイ紙は、以前よりはるかに充実してきている感がある。 お世辞ではなく、読むべき記事が多いのだ。<90歳の壁>をこえた…
-

連載11875回 歩行の技法を考える <5>
(昨日のつづき) <ホモ・モーベンス> 人間は歩く動物である。いかに近代社会が技術化されても、否、技術化されればされるほど人間は歩くことに執着する。 歩くことをやめた人間は、夢の中でも歩く。…
-

連載11874回 歩行の技法を考える <4>
(昨日のつづき) 昔、といっても昭和の前期、つまり戦前、戦中のことだが、陸軍には歩兵という兵種があった。 要するに軍の中核をなす部隊である。文字どおり歩く兵隊だ。 近代の軍隊では兵士は軍用…
-

連載11873回 歩行の技法を考える <3>
(昨日のつづき) 杖を使うようになってから、もう何年かが過ぎた。 いまでは、杖は、すでに体の一部だ。杖なしでは、ほとんど歩けないのが現状である。 杖といい、ステッキといい、古くから人々は杖…
-

連載11872回 歩行の技法を考える <2>
(昨日のつづき) <技法>などと小洒落た題をつけたが、これは昔、大学生のあいだで<ナニナニの技法>などという本が流行ったのを真似したイタズラである。 医学理論も全く無視した勝手な体験記だから、常…
-

連載11871回 歩行の技法を考える <1>
私が左脚に問題をかかえるようになってから、どれくらいたつだろう。 20、30年、いやもっと以前から脚部に異常を感じていた。 戦後70年あまり、病院にいかないことを自分に課してきたのだが、周囲…