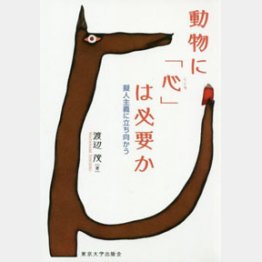「動物に『心』は必要か」渡辺茂著
著者は、ハトにピカソとモネの絵を見せて区別させることに成功し、1995年にイグ・ノーベル賞を受賞した。実験箱にハトを入れてからピカソとモネの絵を10枚ずつスクリーンに映写。ピカソの絵が映写されたときにハトがつつくと餌をあげることを繰り返すうちに、ピカソのときだけつつくようになる。さらに覚えさせた10枚以外の作品を見せたところ、初見の絵でもピカソとモネの絵を見事に判別した。つまり、ハトは絵の持つ共通の性質を覚えていたということだ。
この結果を見ると、動物にも人間と同じような「心」があると思ってしまう。自分のペットが笑ったような表情をするとうれしがってると思うのは、動物がヒトと同じような行動をすると、その背景にある意識もヒトと同じだと類推してそれを「心」と表現するからだ。
しかし著者は、それを心とするのは擬人主義的解釈であり、動物の行動を正確に示すものではないという。この擬人主義がどうして生まれてきたのかを進化論の受容の経緯を踏まえて概説し、併せて反擬人主義を掲げたスキナーの行動主義についても説明していく。
このあたりは専門的で議論についていくのは大変なのだが、科学にとって、本来は排除すべき擬人主義という考えがいかに執拗にまとわりついてきたのかという歴史を知ることができる。
比較的わかりやすいのは「クレバー・ハンス」の例だろう。19世紀末、ベルリンに「賢いハンス」というウマが登場した。ハンスは飼い主のドイツ語を理解し、首を左右に振ったり、ひづめで床を叩くことで計算や文字の読み書きもできると評判になった。当初の調査では何のトリックもないとされたが、心理学者のシュトゥンプらが再調査したところ、飼い主の微細な体の動きとハンスの反応の関係を示してこの問題に決着をつけた。この例でも安易な擬人主義が科学の目を曇らせることがわかる。
「動物」とは何か、「心」とは何かという根源的な問題についても改めて考えさせられる、知的刺激に満ちた書。 <狸>
(東京大学出版会2700円+税)