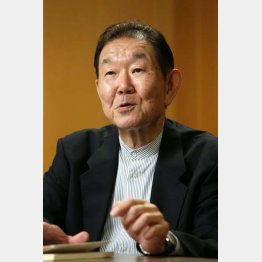「お酒の経済学」都留康氏
コロナ禍によりオンライン飲み会が大盛況だ。酒場と違い、皆と酒やつまみを合わせる必要はなし。ビールに日本酒に焼酎、ウイスキーやワインなど多種多様な酒が画面に映る。
「今の日本は手軽にスーパーやコンビニでさまざまな種類の酒が手軽に手に入りますよね。これだけお酒が多様化したのは、日本経済が大きく関わっているからです」
今はコンビニで気軽に買える缶ビールも昔は酒屋さんが瓶ビールのケースを配達していたし、ブームでプレミアがついた焼酎や第3のビールの登場も話題になった。本書ではよくある酒のガイド本と違って、経済学の視点からアルコール業界の盛衰やブームの裏側について解き明かしている。
「日本も戦後、国民の生活が豊かになり、国民酒である日本酒とともに、冷蔵庫の普及が追い風となってビールの消費量も増えていきました。しかし、1ドル360円時代が終わった1973年を境に日本酒は落ちていきます。ライバルが増えたからです。高度経済成長が続き、今まで高根の花だったウイスキーが手に入りやすくなり、また南九州の焼酎・さつま白波が大規模な宣伝をしたことで全国に焼酎ブームが広がりました」
ビールと日本酒の2大時代が終わり、群雄割拠の戦国時代へと突入すると、所得の上昇に比例してアルコール全体の消費量は増えていった。
ところが、1990年以降にバブル経済がはじけると、家庭で真っ先に削られたのはアルコールであった。成人1人当たりの年間酒類消費量が92年の101・8リットルをピークに2018年には79・9リットルと2割以上も減少したのだ。
「その後の不景気はお酒にとっても『失われた20年』となりました。日本人が酒を飲まなくなった理由は、所得の減少だけではなく、飲酒適齢層とされる人口が減ったことや健康志向の高まりといった社会要因も考えられます」
ビールの生産量はバブル時の半分になり、何度かブームを迎えた焼酎もゆるやかに落ちていく。日本酒に至っては2018年までの45年間で生産量が3分の1に激減した。
「日本酒の消費量がここまで落ちた要因のひとつは、大手メーカーが中小の酒を買い入れる『桶買い』をして不足分を補い、それらをブレンドしたため、味がどこのメーカーも似てしまう『同質化』のワナに陥ったからなんですね。もうひとつは、日本酒や焼酎は既存の蔵元を守るため、戦後、国が新規に製造免許を出してこなかったことも停滞の要因です」
本書では、競合他社などを分析し、自らの市場の位置を決める「戦略的ポジショニング」を体現した「獺祭」と「新政」を好例として紹介しながら、市場を再活性化するためのイノベーションの必要性を説く。「獺祭」で有名な旭酒造は普通酒をやめ、純米大吟醸に特化し、海外に飛び込み営業に行き、輸出に活路を見いだした。また、新政酒造は地元の米にこだわり、強いメッセージを打ち出すなど、最近の中小の若手経営者は切磋琢磨している。
しかし、それはあくまで跡継ぎである「子」による改革であり、外部からの新規参入が認められれば、もっと刺激が起きるはず、と著者は期待を寄せる。
「ビールやウイスキーは新規参入が認められたことで、地ビールブームが起こり、ウイスキーの蒸留所も各地に増えました。最近、日本酒もようやく輸出に限っては新規にも製造許可を出すようになりましたが、いまだに日本で造ったのに国内で販売できないというのは不思議ですよね。徐々に認められていくと思いますが……」
ほかにも、ビール各社のシェア争いや海外から評価の高い日本のウイスキーなどについても解説。酒好きにはなんとも興味深い一冊だ。
(中央公論新社 820円+税)
▽つる・つよし 1954年、福岡県生まれ。一橋大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。現在、一橋大学名誉教授、新潟大学日本酒学センター非常勤講師。著書に「製品アーキテクチャと人材マネジメント―中国・韓国との比較からみた日本」。