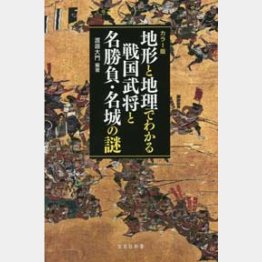「地形と地理でわかる 戦国武将と名勝負・名城の謎」渡邊大門編著/宝島社
関ケ原の戦い、羽柴秀吉と明智光秀の山崎の合戦、川中島の合戦など、戦国時代の戦には「地名」が大きな意味合いを持つ。本書はそれらの舞台がいかに選ばれたかということを歴史的考証とともに記す。
歴史、特に戦国時代好きからすると「なぜこの場所が重要だったのか?」という疑問は常にある。そこを解説していくのである。項目を挙げると「それ知りたい!」となるだろう。
◆なぜ、鉄砲は種子島に伝わったのか
◆なぜ、川中島で武田と上杉が戦ったのか
◆なぜ、桶狭間で信長と今川義元は戦ったのか
◆なぜ、秀吉と光秀は山崎で戦ったのか
◆なぜ、関ケ原合戦で西軍は大垣城を拠点にしたのか
こうした歴史の「場所」について55の項目で解説している。皆さんも経験があるかもしれない。たとえば、東海道新幹線では「関ケ原で雪がすごいため、徐行運転をします」といったアナウンスが流れることがある。となると、「ここで戦った武将たちは一体どのような状況だったのだろうか……」と。サントリーの山崎蒸溜所でウイスキーを飲もうとするため、駅に降り立つと「ここで羽柴秀吉と明智光秀が戦ったんだな……」などと思う。
こうした形で我々は戦国時代を含めた歴史と現在の一致点を見いだし、感慨を深くするが、本書は戦国武将がその場所を選んだ理由をつぶさに解説する。つまり、歴史書でありつつも、観光ガイドブックでもあるという実に稀有な本なのである。
現在、私は佐賀県唐津市在住だが、唐津といえば秀吉の朝鮮出兵で知られる「名護屋城」の地元である。こうした記述がある。
〈なぜ、秀吉は名護屋を拠点として選定したのだろうか。名護屋は玄界灘を望む海上交通の要衝であり、松浦党が中国や朝鮮半島との交易を行うため、交易拠点の一つとしていた。それゆえ港の確保が容易であり、大規模な軍勢を輸送する船舶も停泊可能だった〉
歴史好きであれば誰もが「表面だけ」知っているであろう合戦についての疑問に、著者は合理的な理由をあげて、「だからこの場所が選ばれたのだ」と解説をする。
駿府城を本拠としていた徳川家康がなぜ当地を本拠にしたのかに加え、後には江戸に拠点を移す決断をしたのか、といったことも含め、歴史の点を線でつなぐ作業も行っており、豆知識や飲み屋談議において有用な本になり得るだろう。あと、新書なのにカラーなのも良い。 ★★半(選者・中川淳一郎)