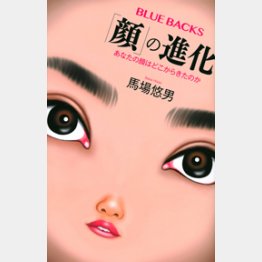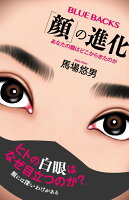「『顔』の進化」馬場悠男著
顔とは「身体の部分(器官)のうち目、鼻、口、耳などが集まっている領域」である。その定義でいえば、イヌ、ネコ、スズメやカラス、その他ヘビやカエル、マグロなどにも顔があるといえる。しかし、クラゲ、ヒトデには顔がない。タコやイカになると、目の周りの部分を顔だといえなくもないが微妙だ。では、多くの動物が持つ「顔」はなぜできたのか。
著者によれば「はじめに口ありき」ということになる。つまり、食物に最初に近づく前端が口となり、効率的に食物を探しとらえるために視覚、聴覚、嗅覚などの諸器官が口の周囲に集まって顔となる。となると、食物のとらえ方、食べ方によって顔を構成する諸器官の位置が変わり、顔のつくりも違ってくる。
たとえばウマ。ウマは脚が細長く、敵を警戒しながら立ったまま地面の草を食べるので、顔と首の長さの合計が脚より長くなければならない。しかし草を臼歯(きゅうし)で噛むために頬の筋肉が発達しているから顔に近い首回りは太く重い。それゆえキリンのように首を伸ばすと重くなりすぎて得策ではない。そこで顔を伸ばせば軽くて済む。こうして馬面が出来上がる。一方ネコは獲物に強い力で噛みつくために顔が幅広くて短く、丸い。
ヒトの顔もまた食生活によって変化しつつ現代に至っている。日本人の顔の変遷を見ても、縄文人は彫りが深くて四角い顔で歯が小さく、その後やってきた渡来系弥生人は平坦で長円の顔で歯が大きい。その2系統が混合し徐々に「日本人」の顔を形成していくのだが、どちらも硬いものを食べていたため、顎の骨がしっかりしていて歯並びも良く側頭筋や咬筋(こうきん)が発達していた。
それが時代が下るにつれて、軟らかいものを食べるようになると顔の幅が狭く、構造的に咀嚼(そしゃく)力が弱くなった。このままいけば未来の日本人は顎が細く口腔内容積が狭まり、睡眠時無呼吸症はじめ、さまざまな障害を起こすことになるという。それを防ぐために給食に硬い食物を出して顔を鍛えることを提言している。
なるほど、顔の話はなかなかに奥が深い。 <狸>
(講談社 1100円)