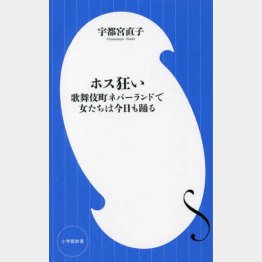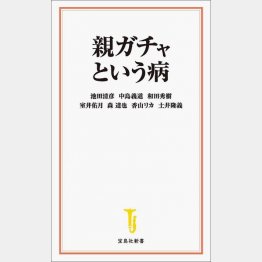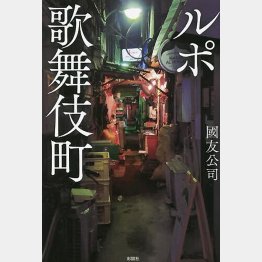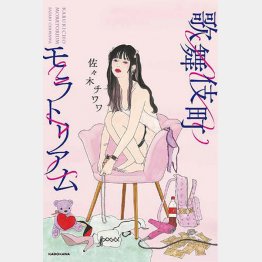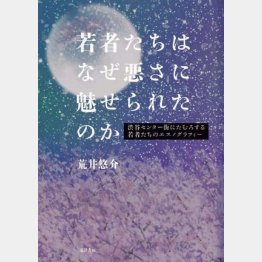若者の生態がわかる!いまどきのJK本
「ホス狂い」宇都宮直子著
「ホス狂い」宇都宮直子著
ホストに入れあげて貢ぐのが「ホス狂い」。「歌舞伎町ネバーランドで女たちは今日も踊る」と副題された本書の著者は週刊誌の芸能リポーター。2000年代初頭、駆け出し記者の著者はホストクラブへの潜入取材を命じられたが、当時は芸能人ら一部だけの現象だった。それがいまや「ホス狂いはブランド」と豪語し、最低でも一晩で200万円も使う女たちが少なくないという。
19年5月、20歳のホストを包丁でめった刺しにした21歳の女が「好きで好きで仕方がなかった」の言葉とともに血まみれの相手を横にした自撮り写真をSNSに上げた。著者はその後、店に復帰した被害者にインタビューし、そこから歌舞伎町の実態に分け入っていく。
ホストに入れあげる女たちはたいてい「#ホス狂い」をつけて発信。「ホス狂いユーチューバー」の有名人もいる。
自殺未遂騒ぎを繰り返しながら心理的な依存関係で突っ走る女たち。歌舞伎町は彼女らの「アジール」(避難場所)だと著者はいう。
(小学館 990円)
「親ガチャという病」池田清彦ほか著
「親ガチャという病」池田清彦ほか著
人間誰しも、どんな親のもとに生まれるかわからない。金持ちの親ならラッキーだが、貧乏やDVの親ならハズレ。「親ガチャ」はそういうあきらめを吐露したネットスラングだ。本書は新書の編集部が精神科医や社会学者、作家ら7人から得た談話や寄稿でまとめたミニ論集。
昭和のオヤジなら、矢沢永吉の「成りあがり」ばりに底辺からでもなにくそとのし上がれとハッパをかけたくなるだろうが、格差の過酷な現実を前にした若者たちはそうはいかない。本書は「キャンセルカルチャー」「ルッキズム」「反出生主義」などさまざまなキーワード別で現代の社会病理を分析する。
親ガチャ論は冒頭の書き下ろし論考(土井隆義)で展開されるだけだが、全体に目を通すと若者たちをとりまく社会病理は、ほどくことのできない地下茎のようにからみ合っているのがわかる。
「親ガチャ」はあきらめ以上の絶望を表しているのかもしれない。
(宝島社 990円)
「ルポ 歌舞伎町」國友公司著
「ルポ 歌舞伎町」國友公司著
国立大在学中からライター稼業に踏みこみ、あれこれ取材に走り回るうち、いつしか「そっちがわ」の世界の一員になってしまったという著者。大阪のドヤ街・西成に住みこんでルポを書いたあと、今度は歌舞伎町のど真ん中のマンションに暮らして書き上げたのが本書だ。
歌舞伎町の明暗を著者は弱肉強食の「食物連鎖」になぞらえる。この連鎖で最上位を占めるのがホスト。原価7万円の輸入ブランデーを100万円で売り上げる。昔は彼らを安くこき使う店も多く、不平を言うと「辞めたければ辞めろ」の一言だったが、いまでは「入店から3カ月は叱るな」「暴力は禁止」と様変わりしているという。
路上で客を引く黒人のキャッチはナイジェリア、ガーナ、セネガル。ケニア、カメルーンなど出身国別でつながりが強いとも。
異文化探検のような読後感の一冊だ。
(彩図社 1540円)
「歌舞伎町モラトリアム」佐々木チワワ著
「歌舞伎町モラトリアム」佐々木チワワ著
「トー横キッズ」といっても東急東横線の鉄オタではない。新宿・歌舞伎町の旧コマ劇場跡にできた新宿東宝ビルの横に夜な夜な出没する10代女子。中には中学生も交じる彼女らは援助交際で稼いだ金でホストに入れあげ、薬物に手を出し、心中事件まで引き起こす。それが「トー横キッズ」だ。
本書の著者も高校時代から歌舞伎町に出入りし、いまは慶大の現役学生。2021年「『ぴえん』という病」(扶桑社)で彼らの生態を伝えて注目された。本書ではツイッター数本分ほどの短文が中間色のデザインで並ぶ。
「この子は俺のことそんなに好きじゃないのかな、って思ってたらある日いきなり大金を持ってくる子もいれば、あんなに好きって言っていたのに、結局それは自己愛で、見返りがないとわかったとたんアッサリ離れていくような子もいる」
トー横キッズやホストたちのドキュメント要素の強かった前著と比べて、こちらは当事者の声の記録という印象だ。
(KADOKAWA 1650円)
「若者たちはなぜ悪さに魅せられたのか」荒井悠介著
「若者たちはなぜ悪さに魅せられたのか」荒井悠介著
渋谷センター街といえばヤマンバギャルとチーマーであふれたのが1990年代。著者は40代初めの大学助教だが、かつては大学入学と同時に渋谷のイベサー(イベントサークル)に入り、代表まで務めたギャル文化の当事者だ。その後、一橋大大学院に学び、博士号を取得。本書はその博士論文をもとにした学術書。
2009年に「ギャルとギャル男の文化人類学」(新潮社)を出したこともありギャルの文化研究と紹介される著者の仕事だが、本書の内容は若者論、サブカルチャー論と社会的逸脱行動研究にまたがるユニークなもの。巨額のイベント運営に必要な「シゴト」、ワルをきどる「ツヨメ」、フェロモンたっぷりの「チャライ」、そして同時代の半グレにも通じる「オラオラ」の4つの特性にまたがる「悪徳資本」という概念を提唱する。
昔の非行少年と違って高学歴で親も裕福というあたり、実は半グレとも地続きであることがうかがわれる。
(晃洋書房 7040円)