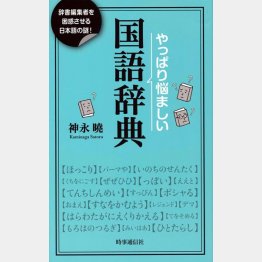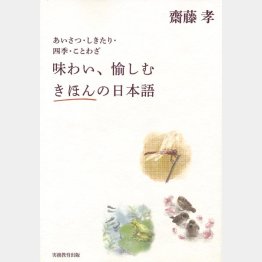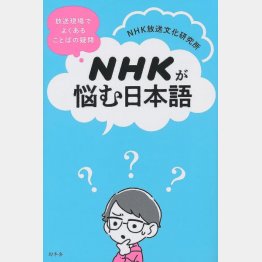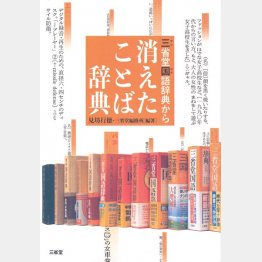日本語の世界を愉しむ本特集
「やっぱり悩ましい国語辞典」神永曉著
アメリカ国務省の「外国語習得難易度ランキング」で、世界で唯一最高難易度ランク+5に分類されている日本語。これを母国語とする日本人でも、分からないまま、間違ったまま使っている言葉があるかもしれない。今回は、辞書編集者や、すでに辞書から消えてしまった言葉まで、日本語の奥深さと面白さが分かる5冊をピックアップしたぞ。
◇ ◇ ◇
「やっぱり悩ましい国語辞典」神永曉著
42年間にわたり辞書編集一筋で日本語と向き合ってきた著者が、時代とともに変化してきた日本語の不思議に迫る人気シリーズ第3弾。
インフルエンザに感染することは「罹る」や「なる」というが、風邪は「引く」という。これはなぜか。「日本国語大辞典」の風邪の項目で、空気の流れである「風」の影響を受けて起こるという説明がある。
また、「引く」は「自分の体に受け入れる」というもとの意味から「吸い込む」に変化したという。つまり、風邪は風を体に吸い込んだために起こると考えられていたということ。昔の人が、風邪が空気感染で発症することを経験的に知っていたことが「風邪を引く」という言葉で分かるのだ。
「ぐれる」の語源はハマグリ、「べっぴん」と「すっぴん」の関係など、読めば読むほど日本語の面白さを感じることができる。 (時事通信社 1760円)
「味わい、愉しむきほんの日本語」齋藤孝著
「味わい、愉しむきほんの日本語」齋藤孝著
挨拶やことわざなどの日本語から、日本人としてのアイデンティティーを再発見する本書。
「こんにちは」は、「は」と書いて「わ」と発音するのはなぜか。漢字で表記すると「今日は」となり、そもそも「今日はご機嫌いかがですか」を省略して使うようになった言葉なのだ。そのため「こんにちは」のひと言にも心の中で「ご機嫌いかがですか」の気持ちを込めることが、日本人の礼儀といえる。
ことわざからも日本人の精神文化が学べる。例えば、蓮如の言葉である「朝に紅顔ありて夕べに白骨となる」。朝は健康だった若者でも、夕方には亡くなって白骨となることがあり、人生の生死は計り知れないということだ。人の命ははかないからこそ生きている時間は尊く、今を懸命に生きることこそが大切だと教えてくれる。
日本人のアイデンティティーは美しい日本語とセットであることが伝わってくる。 (実務教育出版 1760円)
「NHKが悩む日本語」NHK放送文化研究所著
「NHKが悩む日本語」NHK放送文化研究所著
NHKには放送の言葉を研究する文献用語班というグループがあり、視聴者や現場スタッフからの言葉の問い合わせに対応している。本書では、そんな質問の中からピックアップした、使うときに悩みそうな日本語について解説している。
近頃、スポーツ選手や芸能人がよく使う「爪痕を残す」という言葉。「成果を上げる」「印象付ける」といったよい意味で使われているようだ。
しかし、「大辞林」では「爪でかいた傷あと」「災害や事件が残した被害のあと」という意味を載せており、悪い意味のときに使う表現という印象を持つ人もいるはずだ。
NHKの調査では、よい意味で使うことが「おかしい」と答えた20代は18%に対し、50代は49%と大きな差があったという。言葉は変わるものだが、使う相手や場面にはまだ注意した方がよさそうだ。
回数の数え方の「回」と「度」の違い、「年の瀬」は12月何日からなど、言葉の疑問がある人は必読だ。 (幻冬舎 1540円)
「三省堂国語辞典から 消えたことば辞典」見坊行徳・三省堂編修所編著
「三省堂国語辞典から 消えたことば辞典」見坊行徳・三省堂編修所編著
辞典といえば言葉の意味や使い方を調べるためのものだが、本書は何と辞典から消えた削除語だけを集めた辞典だ。
子どもの頃、辞典でエッチな言葉を調べた経験を持つ人も少なくないはず。しかし性俗語は“なかったことにする”という編集方針の強化に伴い、2014年から削除。「愛液」や「前張り」などはもう載っていないそうだ。
進化の速い携帯電話関連の言葉も次々削除されている。「着メロ」に「携帯メール」「ピッチ」「赤外線通信」「携番」などの言葉は跡形もない。「メル友」や「写メ」はまだ生き残っているが、いつ消えるか分からない。
昭和生まれなら学校で習った「士農工商」も今の辞典には載っていない。歴史研究が進み、このような分け方はふさわしくないとされ、もはや教科書にも記述されなくなっている言葉なのだ。
削除された言葉を知ることで、日本の文化や言葉の移り変わりもよく分かる。 (三省堂 2090円)
「面白くて眠れなくなる日本語学」山口謠司著
「面白くて眠れなくなる日本語学」山口謠司著
「ら抜き言葉」は若者の言葉の乱れとして批判されることが多いが、言語学的視点で見ると、この現象はすでに室町時代後期に起こっていたという。
例えば「読む」という言葉。「読むことができる」という可能の意味を表す場合、古語では「読むる」、室町以降は「読まれる」となった。さらに、「お読みになる」は古語で「読まる」だが、室町以降はこれも「読まれる」となってしまった。
そこで混同を避けるため、可能を意味する「読まれる」の「まれ」が「め」に変化。「読める」になったというわけだ。ら抜き言葉は聞き手(読み手)に意味が伝わりやすい一面もあり、川端康成も小説の中でら抜き言葉を連発しているという。
清音と濁音の使い分けや16種類もの発音がある「ん」、主語を省いても伝わる文法など、世界でも難解といわれる日本語を母国語とする日本人。しかし、まだまだ知らない日本語の奥深さがありそうだ。 (PHP研究所 1540円)