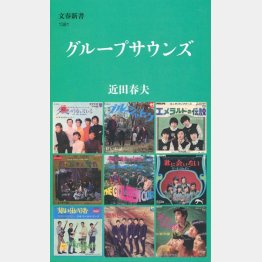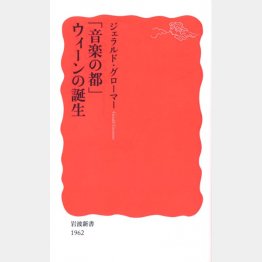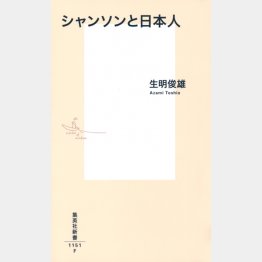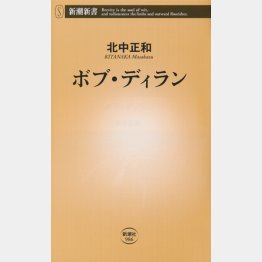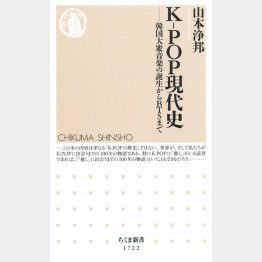♪聴かず嫌いじゃもったいない!最新音楽本特集
「グループサウンズ」近田春夫著
日常に音楽が欠かせないという人でも、聴く曲は好きなジャンルに偏りがちで、気にはなっていても、ほかのジャンルまでなかなか触手が伸びないものだ。ということで、今週は読者を聴く気にさせてくれる音楽本をお手軽な新書で集めてみた。
◇ ◇ ◇
「グループサウンズ」近田春夫著
昭和40年代前半、大ブームを巻き起こしたグループサウンズ(GS)。最盛期には100を超えるグループがレコードデビューを果たしたというが、ブームの期間は短く、昭和46年にはほとんどのグループが消滅。その興隆はわずか5年ほどだった。本書は、その歴史を掘り下げながら、ブームの深層に迫るGS論。
昭和39年、米国アストロノウツの「太陽の彼方に」のヒットがエレキブームを受容する土壌を日本に育てた。さらに映画「エレキの若大将」(昭和40年公開)に触発され、エレキギターを弾く若者が増え、オーディション番組を勝ち抜いた「ザ・サベージ」が、GSのトップバッターとして世に出る。以降、ザ・スパイダースやザ・タイガースなど大ヒット曲を生んだ9組のGSの生い立ちから消滅に至るまでをその音楽性とともに論じる。元ザ・タイガースの瞳みのる氏ら、当事者へのインタビューも併録。
(文藝春秋 990円)
「『音楽の都』ウィーンの誕生」ジェラルド・グローマー著
「『音楽の都』ウィーンの誕生」ジェラルド・グローマー著
ウィーンは古くから音楽の盛んな地であったが、「音楽の都」の呼称が広まったのは意外に遅く、19世紀以降だという。欧州の重要な音楽都市として認識されるようになったのも、音楽家のハイドンやモーツァルトらが活躍した18世紀後半のことらしい。
「音楽の都」に至る萌芽のひとつは、17世紀後半、諸侯によって宮廷や教会が増築されたことにある。それらは音楽演奏の会場となり、音楽文化発展の下支えとなった。ハプスブルク家の皇族は洗練された音楽文化を先頭に立って振興し、貴族たちは権力を誇示するため、楽団を創設し、また音楽家を経済的に支援していく。活躍の場を探す音楽家にとって、魅力的な都市となっていった。
劇場の発展、音楽教育の普及、演奏会や舞踏会の発展などさまざまな要素が重なり音楽の都として花開いていったウィーンの姿を、当時の史資料を駆使し解き明かしていく。
(岩波書店 1100円)
「シャンソンと日本人」生明俊雄著
「シャンソンと日本人」生明俊雄著
日本で初めてシャンソンが歌われたのは、1927(昭和2)年、宝塚少女歌劇団(現宝塚歌劇団)のレビュー「モン・パリ」でだった。
同時期、トーキーの開発を機に主題歌にシャンソンを用いたフランス映画によっても、日本にシャンソンが急激に広がる。さらに、レコードと蓄音機の普及によってシャンソンは日本のポピュラー音楽のジャンルのひとつとして成長していく。ジャズやタンゴなど外国生まれのほかの音楽とは異なり、シャンソンの場合はその多くが原語のフランス語ではなく日本語による訳詞で歌われており、それが日本での流行を促した。
戦後、岩谷時子やなかにし礼など後に流行歌の作詞家として活躍する人たちが、シャンソンの訳詞家として活躍。名曲の名訳詞を送り出し、シャンソンブームが到来する。
しかし、1980年代に入ると、発展を続けてきた日本のシャンソンの歩みに陰りが見え始める。
日本人とシャンソンの100年に及ぶ歴史と変遷を、関わった人物たちのドラマとともに描く通史。
(集英社 1100円)
「ボブ・ディラン」北中正和著
「ボブ・ディラン」北中正和著
80歳を超え、いまなおコンサートツアーを続けるボブ・ディランの音楽人生を振り返り、その魅力と偉大さを語る入門書。
1941年にアメリカのミネソタ州で生まれた氏は、大学時代にフォークソングに傾倒。61年、フォークの父ウディ・ガスリーに会いたい一心で大学を中退してニューヨークへ。そこで大物プロデューサーのジョン・ハモンドに才能を見いだされ62年にデビューするが、最初のアルバムはわずか数千枚しか売れなかったという。
しかし、翌年、セカンドアルバム「フリーホイーリン・ボブ・ディラン」と収録曲の「風に吹かれて」などが評価され、一躍フォークのプリンスとして注目を浴びる。その後ロックに転身、65年に発表した「ライク・ア・ローリング・ストーン」は全米チャート2位のヒットとなる。
各作品を解説しながら、彼の音楽がどこから生まれ、それをどのように録音物に定着させ、コンサート活動で表現してきたのかを語り尽くす。
(新潮社 836円)
「K-POP現代史」山本浄邦著
「K-POP現代史」山本浄邦著
昨年、活動休止したBTS(防弾少年団)以外にも、NCTやBLACKPINKなど、グローバルに活躍するK-POPグループは複数存在する。2020年代に入ってからも、次世代グループが続々とデビューして、世界の主要チャートにランクインしている。
なぜK-POPは世界各地で多くのファンを獲得し、ヒットを連発できるのか。その快進撃の秘密を分析した音楽テキスト。
朝鮮が日本の支配下にあった1920年代までさかのぼり、K-POPの源流である韓国の大衆音楽の誕生と発展を概観。以降、チョー・ヨンピルら韓国人歌手が演歌歌手として日本に進出した背景などにも触れながら、民主化以降の韓国社会においてヒップホップ文化とアイドル文化が結合してK-POPが誕生していく過程を詳述する。
日本の韓流ブームや戦後最悪といわれる日韓関係悪化の中でのブーム再来なども視野に、K-POPの形成・発展・越境していくプロセスを追いながらその歴史的アイデンティティーに迫り、快進撃の理由を明らかにしていく。
(筑摩書房 946円)