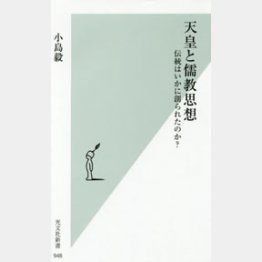「天皇と儒教思想」小島毅著
伝統ということばを辞書で引いてみると、「ある民族や社会・団体が長い歴史を通じて培い、伝えて来た」(「広辞苑」)ものとある。つまり、昔から続いてきたものが伝統だというわけだ。
ところが、伝統とされているものが実は最近になって生まれた例は少なくない。たとえば、神社で二礼二拍手一礼が正式な作法だとされ、皆それに従っているが、このやり方が普及するのは最近のことである。神社界をまとめる神社本庁がその普及をめざしたことによる。神道が日本に生まれてからの伝統だと考えてしまうと、大きく間違うことになる。
本書で最初に取り上げられている天皇の稲作りになると、なんと昭和天皇が生物学的な関心からはじめたものである。だから、田植えを行う天皇はワイシャツ姿で長靴をはいている。まるで神事の形式をとっていないのだ。
これをきっかけに、本書では山稜、祭祀、皇統、暦、元号が取り上げられる。
古代の天皇を埋葬した山稜(いわゆる古墳)への関心が生まれたのは江戸時代になってからである。皇居にある宮中三殿の一つ、代々の天皇や皇族の霊を祭った皇霊殿も、明治になってはじめて生まれたものである。
今日のような形で代々の天皇が定められたのも明治になってからで、それまでは神功皇后も天皇のなかに加えられていた。
どの暦を使うかは重要だが、明治政府はそれまでの伝統的な暦を廃して、あっさりと西洋のグレゴリオ暦を採用してしまった。だから、七夕が梅雨のさなかにやってきてしまうのだ。
著者の専門は中国思想史なので、とくに皇霊殿の問題や元号のことになると、中国儒教の知識が生かされている。
元号は吉事が起こったり、災いが起こったとき、改元して、時代の空気を変えるためのものでもあるが、明治になって天皇の代が続くあいだ改元しないというやり方が定められた。そこには、儒教を革新した朱子学の影響があり、それは明の制度を真似たものなのである。
来年の天皇の代替わりをめぐって混乱が生じているのも、中国では清朝の滅亡で元号そのものが消滅し、モデルが失われたからかもしれないのである。(光文社 860円+税)