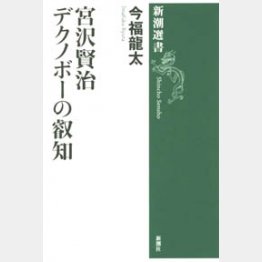「宮沢賢治 デクノボーの叡知」今福龍太著
1921年1月23日、25歳の宮沢賢治は家出して上京するが、8月、妹トシの病気の知らせを受け急きょ、花巻に戻る。この半年余りの家出は賢治の大きな転換点とされ、以後、数多くの童話や詩が書かれていく。そうして出来上がった作品のすべてに現れる語句の中で、もっともたくさん使われているのは「風」で、次いで「空」「鳥」そして「すきとほ(お)る」だという。つまり「すきとおった風が空を鳥の飛翔とともに吹きすぎてゆく……」というのが賢治の創世する風景だと、著者は指摘する。
これまで宮沢賢治については、多くの評伝や評論が書かれてきた。それらを通じて宮沢賢治という人とその作品のイメージが固定してきた。
本書は、宮沢賢治をそうした「馴染みの所有物」から解放し、未完の草稿が示す「躍動する揺らぎと未知の可能性」を、現代社会において照らし出そうという試みだ。
著者が手がかりとするのは〈海〉〈風〉〈石〉〈北〉といった賢治の作品に頻出する語句で、表題の〈デクノボー〉もその一つ。「ミンナニデクノボートヨバレ……サウイフモノニ/ワタシハナリタイ」という「雨ニモマケズ」の一節が有名だが、従来、このデクノボーに同化したいという賢治の心的傾斜は法華経の影響と解されてきた。著者はこの通説から踏み出して、賢治と同時代人のカフカ、ベンヤミンが共に「誰かを助けるためには、人は愚か者でなければならない」という命題を提示していて、それが賢治のデクノボーと通底していることを明かしていく。
その他、石牟礼道子、ジョージ・オーウェル、ウィリアム・モリスらとの共振ぶりを描くことで、賢治をより広い地平の中に連れ出す。新たな賢治学の萌芽を示す労作。 <狸>
(新潮社 1600円+税)