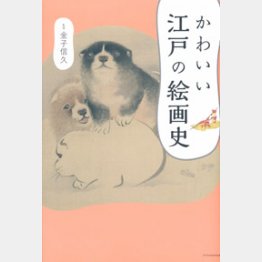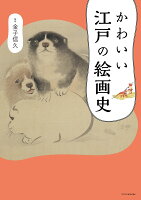「かわいい江戸の絵画史」金子信久監修
「カワイイ」や「マンガ」はいまや世界共通語だが、そのルーツともいえる日本絵画の中の「かわいいもの」は、美術史では豪華や厳かな美術に比べて「ちょろい」「低俗」と思われてきた。しかし、「かわいいものがどう表現されてきたか」という視点から日本美術を見渡すと、驚くような画家の技術やアイデアが浮かび上がってくるという。
本書は、輝かしい作品が多く生まれた江戸時代の「かわいい美術」にスポットを当て、その魅力を説くアートガイド。
江戸時代前期に始まる「かわいい絵画」の草創期、その中心を担ったのは俵屋宗達だった。国宝「風神雷神図屏風」の作者の俵屋は、一方で「やわらかな水墨画」も得意とした。その最大の特徴は「単純化とデフォルメ」によって作り出される「やわらかな形」だという。
わらびの萌える地面を嗅ぎながらよちよちと歩く黒い子犬を描いた「狗子図」や、本来は勇猛で怖いはずのものをあえてかわいく描いた「虎図」など、なんともゆるく心がほどけていくような絵なのだが、そこには禅の思想が込められているという。実は禅の思想は、かわいい美術を生み出す源にもなったのだそうだ。
以後、宗達の流れをくむ伊藤若冲の「河豚と蛙の相撲図」をはじめ、現代のヘタウマにも通じる与謝蕪村、「リアルでかわいい」という新しい描き方を発明した円山応挙、「ゆるくてかわいい」長沢蘆雪が描く子犬、そして極め付きはうまい下手を超越して突っ走り「その暴走感で見る者に快感を与える」仙厓義梵まで、16人の作品を鑑賞する。
筏をこぐ金魚(歌川国芳)やキリンのような鹿(三浦樗良)など、見ているだけで楽しい気分になってくるようなキャラクターが勢ぞろい。日本人のかわいい文化のルーツがここにある。
(エクスナレッジ 1800円+税)