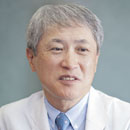「心筋保護液」はさまざまな試行錯誤の末に確立された
基礎医学的なアプローチとして、心臓摘出までドナーの体温が25度、心臓は28度になるまで冷却されました。低温にして心筋細胞の代謝を落とすためです。さらに、取り出された心臓は10度の乳酸リンゲル液に浸されました。ナトリウム、カリウム、カルシウムなどを水に溶解したもので、体液や電解質の補給に使われる薬液です。こうした試行錯誤の末、移植手術は成功したのですが、結局、患者さんは18日間しか生存できませんでした。
心臓が停止している間、いかに心筋にダメージを与えずに済むか──心筋保護は心臓手術にとってさらに大きなテーマとなります。そんな中、1970年代になって英国のセント・トーマス病院が心筋保護液の研究を始め、新たな高カリウムの心筋保護液が開発されます。カリウム、カルシウム、ナトリウムなどの成分のほか、緩やかに心臓の収縮を落としていくマグネシウムが加えられました。これは「セントトーマス液(第1液)」と呼ばれて広まっていきます。さらに、1981年にはpHと成分の調整を行った第2液が登場し、いまも世界中で使われています。
もうひとつ、心筋保護液として広く使われているのが「GIK液」です。含まれている成分のグルコース、インスリン、カリウムの頭文字をとって名付けられたもので、安価なうえに施設内での調製もそれほど難しくないため、1980年代くらいまでは日本でもGIK液を主体として使っている施設が多くありました。