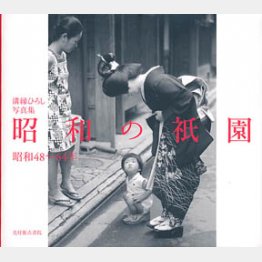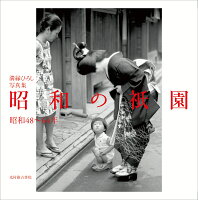「昭和の祇園昭和48~64年」溝縁ひろし写真・文
コロナ禍の前、日本有数の観光地として国内外から多くの観光客を集めていた京都の祇園。その魅力は、日本の昔ながらの町並みと、長い歴史に培われた伝統と文化、そして運が良ければ出会えるであろう艶やかな舞妓や芸妓たちの存在であろう。
しかし、近年はあまりにも大勢の人が押し寄せ、静かに日本情緒を味わうこともままならない状況が続いていた。
本書は、祇園が祇園らしかった時代に町の日常を定点撮影した写真集。
撮影が始まったのは今から半世紀近くも前の昭和48(1973)年6月から。メインストリートの花見小路を歩く2人の舞妓のそばを配達と思われるバイクが通りかかっている。他に人の姿はなく、閑散とした景色に隔世の感を抱く。
続くページでは、玄関先で届いたばかりの夕刊を開いていた和装の女性と、通りがかりの舞妓が会話をしている。他にも、玄関先に出した床几で夕涼みをするお茶屋の女将さんたちや、お座敷の帰りなのだろうか「だらりの帯」のまま薬局で買い物をする舞妓など、私たちの知らない花街の日常の風景が並ぶ。
一方で、祇園には一年を通してさまざまな行事があり、折々に別の表情を見せる。正装の黒紋付きの芸舞妓が勢ぞろいする1月7日の「始業式」にはじまり、普段の着物姿とは異なり、思い思いの仮装をして気が合う仲間と座敷を渡り歩き、その日のために用意した芸を披露する節分の「お化け」や4月の「都をどり」から、8月1日の「八朔」、祇園を愛した歌人・吉井勇をしのぶ「かにかくに祭」、師走の南座での顔見世を揃って観劇する「顔見世総見」、そしてお正月の準備を始める日とされる12月13日にお世話になった師匠に挨拶に行く「事始め」など。
各行事を大切にしながら生きる祇園の町と芸舞妓たちの姿をカメラに収める。
そんな祇園の表だけでなく、「都をどり」のために集まっての稽古風景や、普段のお座敷前の着付けや化粧など、華やかな日常の裏の部分も紹介。
中には、もう行われなくなった「おことうさん」と呼ばれる大晦日の挨拶回りで配られる「福玉」をたくさん持った芸妓や、携帯電話もない時代であるがゆえに、黒電話で置き屋に定時の連絡を入れる舞妓や、大きな外車のハイヤーで移動する姿など、今では見られなくなった風俗も記録されている。
また、舞妓たちの中学の卒業式や成人式などプライベートから、舞妓デビューである「店出し」や、舞妓から芸妓になる「襟替え」、事情があって芸妓をやめる「引き祝い」など、それぞれの人生の節目も追う。
一方で、舞妓が履く「おこぼ」や、月ごとに替わる花簪をつくる職人など、花街を支える人々の仕事ぶりなどにも目を向け、祇園のすべてを撮りつくす。
撮影当時からお茶屋は3分の1近くに、芸舞妓も半数以下になってしまったという。昭和が終わる最後の日まで撮り続けられてきた、昭和の祇園のありのままの姿を伝える貴重な写真集だ。
(光村推古書院 2640円)