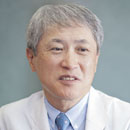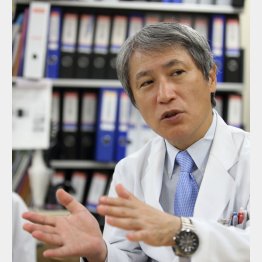心不全の「緩和ケア」はこれからどんどん進化していく
前回お話ししたように、心不全に対する緩和ケアは、患者さんのQOLの維持・向上のためにどのような医療が有効かのエビデンス(科学的根拠)がまだ少ないのが現状です。そのため、がんの緩和ケアとは違って、状況に応じてどんなケアを行えばいいのかなど、具体的な方法がきちんと固まってはいません。ただ、それまで心臓の治療を専門にしていた医師が緩和ケアを行うようになっていけば、どんどんデータが増えていき、より有効な対応が構築されていくでしょう。
たとえば、身近な問題として自宅での食事をはじめとした栄養管理が挙げられます。心不全が進行すると、食欲がなくなって食事量が減ってしまいます。心機能が低下して血液を肺に送る力が衰えることで、腸管に血液がたまってむくみが生じ、腸の動きが悪化するためです。
また、肺での酸素と二酸化炭素のガス交換が阻害されることで呼吸障害や倦怠感が生じ、これも食欲不振につながります。
食事が減って栄養状態が低下すると、全身の筋肉量が減少します。そうなると血圧の調節力が低下し、重要臓器への血流確保を優先することから心臓の負担が増大するうえ、加えてほかの臓器にも障害が起こります。心不全の患者さんに栄養障害や体重減少を認める状態は「心臓悪液質」と呼ばれ、その終末像がサルコペニアで、予後が悪くなることが知られています。逆に心不全の患者さんに栄養介入を行うと、死亡率や再入院率が低下したという報告もあるように、心機能を低下させずQOLを維持するためには、食事=栄養がとても重要なのです。