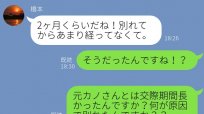「流されゆく日々」12000回記念 五木寛之さん×日刊ゲンダイ対談(前編)
「作家として一番忙しいときによくも連載依頼したものだと」
寺田 ありがとうございます。連載の始まりは、前々社長の川鍋孝文さんの依頼でした。改めて1975年当時は五木さんにとってどういう時期だったかといいますと、1967年に「蒼ざめた馬を見よ」で直木賞を取られて、69年には「青春の門・筑豊篇」の連載が始まり、76年には吉川英治賞、「戒厳令の夜」も出された。作家としては最も脂がのりきって一番忙しいときなんですね。そんなときに、創刊したからといって、川鍋さんはよく新聞連載を頼めたもんだなと、今考えると、大胆すぎるというか驚きます。
五木 川鍋さんとは個人的にもね、非常にいい友人だったんですよ。ですから、「ひとつお願いしますよ」というようなことでね。「すぐつぶれますから大丈夫ですよ」なんて言われて(笑)、それじゃあって始まったわけです。
寺田 五木さんは川鍋さんが亡くなったとき、追悼で「自由な風のような人だった」と書かれています。私たち後輩から見ると川鍋さんは一種の根無し草的なとこもあって、お二人が親しくなったのは作家と編集者という立場を超えたシンパシーというか、共通項のようなものがあったのかなと思いました。
五木 ありましたね。特に自由というものに関しての考え方が似ていたんです。ジャーナリストなんだけど根っこは文学青年で、酔っぱらうとランボーの詩をフランス語で朗読したり、いつまでも青年みたいな気分の抜けない人で、その辺が面白かったですね。川鍋さんのそういうキャラクターを日刊ゲンダイはずっと引き継いでいるんですよ。それが僕が日刊ゲンダイに愛着を持っている理由の一つなんです。川鍋という個性が脈々と現在の紙面に流れている。これがなくなったら、やっぱりここまで連載を頑張ってやるという気力はなかったと思いますね。
寺田 川鍋さんのDNAをひと言で言い表すのは難しいんですけど、まず1つはいい加減なんですね。
五木 たしかに(笑)。
寺田 それからアウトローなんですよ。でもイデオロギーうんぬんではないんです。川鍋さんがよく言ってたんですが、目線は低く。要するに上から見ちゃだめだと。ジャーナリズムとか、そういうこだわりを持たずに、もっと自由にと。それからしなやかに、というのも川鍋さんはよく言っていました。そういうことを思い出すにつれて、何か五木さんが連載で書かれていることとも、少し似ているところがあるのかなと思ったんですが。
五木 僕はやっぱり川鍋さんが残したものを自分は引き継いでいる、そんなふうに思っていますね。
寺田 え、五木さんが?
五木 ええ。僕は、彼が残したものをできるだけ大事にしてるんです。高いところから俯瞰して物を考えたり書いたりするのではなくて、草の間を這う虫のように、這いずり回って仕事をしていくという感覚とかね。ゲンダイの場合は、ちょっと(目線が)低すぎるって(笑)そしりもあるだろうけど。
寺田 うれしいですね。