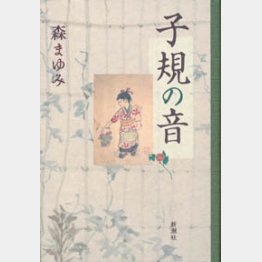「子規の音」森まゆみ著
病苦と壮絶な闘いをしながら、俳句と短歌を革新し、34歳の若さで没した正岡子規。子規の評伝は数多いが、この本はいわゆる伝記とは趣を異にする。
子規が暮らした明治20年から30年ごろの、東京の風景や庶民の暮らしぶりが、詳細に描かれている。
明治維新の前年、松山藩の下級武士の家に生まれた子規は、中学を中退して上京、日本橋、神田、本郷あたりを転々とした後、最後の10年を、根岸に暮らした。
そのころの根岸は、田んぼやねぎ畑が広がり、鳶が舞う農村地帯で、鳥の声も虫の声も身近だった。日々の営みの音、隣家の子どもの話し声も聞こえた。窓を開けると車やバイクの音ばかりの今の東京とは大違い。
旅好きで、芭蕉の足跡を追うなど活発に出歩いていた子規だが、肺結核と脊椎カリエスが進行すると、動くこともままならなくなる。母と妹の助けがなければ、何もできない。それでも、あふれ出るように俳句や短歌を作った。研ぎ澄まされた感覚で町の音を聞き取り、季節の移ろいを感じ、言葉を紡いだ。
病んでなお意気軒高な子規の元には、友人や弟子たちが頻繁にやってきた。死と隣り合わせの身で、子規は精いっぱい、文学の喜びに生きようとした。
子規の俳句や短歌を数多く引用しながら、その背景となった明治の根岸の情趣が、こまやかに描かれる。著者は、地域雑誌「谷中・根津・千駄木」を25年にわたって刊行し続けた編集人。
子規が居た根岸は、著者自身が見た昭和30年代までの風景とつながっている。その記憶と、編集を通じての蓄積が、子規の生きた時代を臨場感をもって浮かび上がらせ、「子規をめぐる五感の旅」へと誘う。(新潮社 2100円+税)