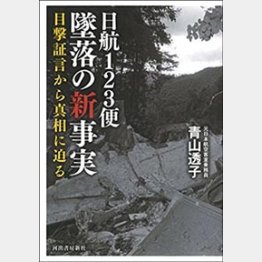日航123便墜落に自衛隊・米軍の影
「日航123便墜落の新事実」青山透子著/河出書房新社
群馬県上野村の御巣鷹の尾根に日航ジャンボ機が墜落してから32年。くしくも33回忌の今年、衝撃的な本が出た。著者は、自分もあの123便に乗っていたかもしれない元客室乗務員である。先輩や同僚の無念を背負うように、安全にも携わるその立場から、著者は次々と、単なる事故として片付けられたあの「墜落」にさまざまな疑問を突きつける。
当時の首相は中曽根康弘で防衛庁長官は加藤紘一だった。運輸大臣が山下徳夫。
著者は「中曽根康弘が語る戦後日本外交」(新潮社)から、次の一節を引く。
「日航ジャンボ機墜落の報告が私に届いたのは、軽井沢から東京に戻る列車の中で午後七時過ぎでした。それで八時頃から首相官邸の執務室に入って、即時に色々な報告を受けたし、こちらから対策の指令も出した。国民に対して政府の正式見解を出すのは、事態の調査に遺漏のない状態で、万全を期してから発表しなくてはいかん。それまでは、私に留めて、私が合図するまでは公式に発表してはならんと指示しました」
そして、事故現場の情報が二転三転したことについては、「実際、静岡に落ちたとか、群馬に落ちたとか、情報がずいぶん迷走していました。米軍もレーダーで監視していたから、当然事故については知っていました。あの時は官邸から米軍に連絡は取らなかった。しかし、恐らく防衛庁と米軍でやり取りがあったのだろう」と語っている。著者も指摘するごとく、首相の知らないところで「防衛庁と米軍でやり取りがあった」のなら、これは大問題である。しかも、墜落現場については、群馬県上野村の村長、黒澤丈夫が政府や県に連絡し、村民もNHKに電話をかけたのに、長野県と報道されていた。
そうした事実を踏まえて著者は、事故機をファントム2機が追尾していたことなどの「隠蔽工作にはある程度の時間がどうしても必要だった」と推測する。そして、報道関係者のトップも何らかの指示を受けていたか、あるいは知らないままに自衛隊から来る情報をうのみにしていたのではないか、と続ける。日本航空もしかりである。さらに「完全炭化した遺体から推測できることとして、ガソリンとタールを混ぜたゲル化液体を付着させる武器を使用した可能性」があり、「墜落直前に赤い飛行機と思われただ円や円筒形に見える物体を目撃した人がいる」ことから、武器を持つ自衛隊や米軍の関与を示唆している。 ★★半(選者・佐高信)