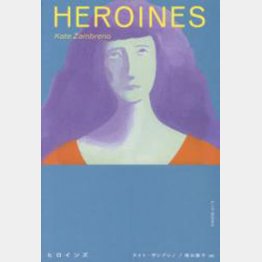「ヒロインズ」ケイト・ザンブレノ著、西山敦子訳
1925年4月に「グレート・ギャツビー」を刊行したF・スコット・フィッツジェラルドは、翌月早くも次の長編に取りかかる。しかしその後、妻のゼルダが精神を病み入退院を繰り返すなどで執筆は難航し、完成したのは9年後の34年。村上春樹が「器量のある小説」と評した「夜はやさし」だ。それに先立つ32年、療養中のゼルダが自伝的な小説「ワルツはわたしと」を発表、その中に長編で使おうとした夫婦のエピソードが使用されていることにスコットが激怒した。
この挿話には苦悩する天才作家とその足を引っ張る病んだ女性といった図式が見えるが、それに猛然と「否」の声を上げたのが著者のザンブレノだ。本書にはゼルダを筆頭に、T・S・エリオットの妻ビビアン、ポール・ボウルズの妻ジェインら、偉大なモダニズム作家の陰に隠れて声を奪われ、精神を病んだ女性たちが登場する。著者は、夫の仕事の関係でオハイオ州の片田舎に閉じ込められている自分と彼女らを重ね合わせ、女性を周縁に押しやり、沈黙を強いていく男性優位社会へのあらがいの声をブログで発信していく。
さらにバージニア・ウルフ、シルビア・プラスという、ともに自死を遂げた作家を加え、ともすれば男性にキャラクター化され、平面化されてしまいがちな女性たちが、狂気という桎梏(しっこく)を抱え込みながらも、書くことで自らの物語を獲得していこうと苦闘する姿を描く。
そう、彼女たちは、自らも書くことで居場所を得ている著者のヒロインたちなのだ。
ゼルダは、スコット死後の48年、入院先の精神科病院の火事に巻き込まれ焼死。それから70年、いまだに医学部の入試においてあからさまな女性差別が行われているという現状に、天国のゼルダは何を思うのだろうか。
<狸>
(C.I.P.Books 2300円+税)