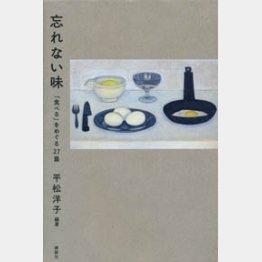食べるのが楽しくなる本特集
「忘れない味」平松洋子編著
日々の暮らしの中で、ささやかな楽しみを与えてくれる、うまい食べ物。こだわりの食材や、とっておきの高級料理はもちろんのこと、なんということのない日常の一品が、明日への力を与えてくれることもあるはず。今回は、忘れられない味、町中華、京都の食、平成の食物語、フランスの日常食をテーマにした食べ物本5冊をご紹介!
唾が出てしまうほど食べ物の描写をするのがうまい作家がいる。しかもそんな彼らの描写は、人間関係や人間性、その人の考え方を浮き彫りにする舞台装置にもなるのだ。そんな食をめぐる作品を収録しているのが本書。たとえば川上弘美の小説「少し曇った朝」では、女が握るおむすびが、恋愛にまでは至らない不確かな男女関係をつなぐ食のツールの役割として登場する。かと思えば、山田太一のエッセー「食べることの羞恥」では、食べることを恥ずかしいと感じる日本人がかつて持っていた感性について取り上げる。
ほかにも伊藤比呂美の描く白玉、益田ミリの社員食堂、吉本隆明の梅など、読み手を刺激する作品計27編。食べることが、時にはエロチックで、時には惰性的、時には死と隣り合わせになるのが興味深い。
(講談社 1800円+税)
「日曜日はプーレ・ロティ」川村明子著
フランスの家庭料理が学びたくて、フランスに渡った著者は日本とは格段に不便なフランスの食生活に遭遇する。いつでもすべてがそろっているコンビニはなく、均一の品質やおいしさが保証されるわけでもない。パンはパン屋で対面で買わなければならないし、日曜日にはスーパーもレストランも多くが定休日になってしまう。そんな不便さを契機に、素材を一から自分好みのものに作り上げていくフランスの食の楽しさ、おいしさに著者ははまっていった。
本書のタイトル「プーレ・ロティ」とは、フランスで出合ったローストチキンのこと。一羽丸ごと焼き上げられる精肉屋の軒先のチキンに象徴される、自由でゆったりとした食にかける時間がなんとも贅沢だ。安くて便利な食を追求しすぎた日本との違いが際立つ。
(CCCメディアハウス 1500円+税)
「旨し、うるわし、京都ぐらし」大原千鶴著
京都で暮らす料理研究家の著者が、これまでの半生を振り返りながら、京都の地で培われた豊かな食生活を紹介しているのが、この本。
著者によれば、京都の味を生み出す基本は、①水が軟水であること②軟水と相性の良い昆布だし文化③夏は暑くて冬は寒いという気候が育んだおいしい野菜④豊富な山の幸と海の幸⑤街のサイズがコンパクトなため新鮮な食材がすぐに手に入る――の5つ。「山菜てんぷら」や「筍と鶏肉とスナップえんどうの炊いたん」など、酒の肴にもなるメニューのレシピも紹介している。
「複雑な味付けをしなくても、旬の素材、だし、調味料の三つの基本がしっかりしていれば、あとは何とでもなります」と語る和服美人の著者から手ほどきを受ける気分で、本書片手に厨房に入るのも悪くない。
(世界文化社 1600円+税)
「いただきます」毎日新聞社会部・著、佐々木悟郎・絵
平成の30年間を振り返れば、「あのころ」の世相と結びついた思い出の食べ物があることに気づかされる。たとえば、史上最年少の棋士・藤井聡太の登場で巻き起こった将棋ブーム。このブームのなか、歴代の棋士御用達の勝負メシとして一躍有名になったのは、老舗うなぎ屋「ふじもと」のうな重だ。栄養いっぱいで腹持ちがいい上、素早くかきこめるとあって、加藤一二三・九段は勝負のたび毎回このうな重を頼んでいたらしい。
本書は、そんな平成の出来事や暮らしと結びついた食べ物を、その時々の人間ドラマとともに紹介したもの。加えて特筆すべきは、香りや温度まで伝わってくる佐々木氏のイラストの完成度だ。汁に浮いた脂まで描かれたホープ軒の豚骨ラーメンなど目にしたら、途端に店に駆け込みたくなること必至。
(ブックマン社 1800円+税)
「夕陽に赤い町中華」北尾トロ著
「町中華」とは、個人経営の大衆中華料理店をいい、安くてたっぷりのボリュームで常連客の胃袋をつかんで離さない。
その魅力といえば、何といってもメニューの多さだ。どこの店も定番もの、単品つまみ系、濃厚でガツンとくる料理などバランスよく、また豊富に揃っているが、これは店を支える常連客たちの好みに幅広く対応してきた結果だという。また開業50年を超えるような店ではカレーライス、オムライス、カツ丼の“非中華トリオ”が揃っている傾向がある。
町中華は第2次世界大戦後に発生し、高度成長期にかけて定着。80年代のチェーン店ブームの中でも、出前と常連客という強みで戦い、生き残ってきた。
「町中華探検隊」の隊長が昭和の食文化「町中華」の歴史と魅力に迫る。
(集英社インターナショナル 1600円+税)