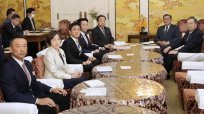戦争指導者は軍需に特化する予算を組めば勝てると盲信した
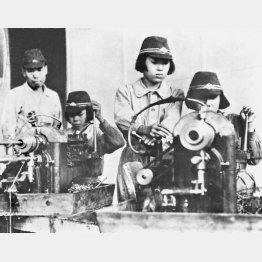
さらに続けるが、アメリカの戦略爆撃調査団報告書(その一部を訳した「日本戦争経済の崩壊」正木千冬訳)を読んでいくと、1941年度と42年度の日本の全生産量は比較的順調であった。40年度の国民総生産は398億円で、2年後の42年度には406億円とわずかに上昇している。この間に対米戦…
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り884文字/全文1,025文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】