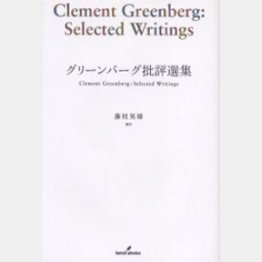ナチスの美学は“美的な成り上がり”趣味
歴史上、独裁者は数あれど、この男ほどの芸術かぶれも珍しいだろう。アドルフ・ヒトラー。ドイツ軍によるパリ占領の際、彼がまず駆けつけたのは大統領府のエリゼ宮ではなく、芸術の華とうたわれたオペラ座だったのだ。
そんなヒトラーの芸術愛好を戦争犯罪と絡めて改めて指弾したのが、先週末封切りの「ヒトラーVSピカソ 奪われた名画のゆくえ」である。
うらぶれた小市民階級から成り上がったナチ上層部に、芸術かぶれが多かったのは周知の事実。アートの目利きを自負する幹部の間で略奪競争が行われ、一般市民を相手に、芸術の理想と堕落を教える展覧会なども企画された。
映画はそのへんを初心者にもわかりやすく解説する一方、ナチスの略奪に欧州各地の画商たちが深く関与していた実態を明らかにする。強権に無理やり従わされた者、権力者に取り入って生き残りと一儲けを企む者……。
目新しい事実などは特に見当たらないが、丁寧な構成と案内役を務めたイタリアの老優トニ・セルヴィッロの存在感で「教育番組」風の退屈さを脱している。
実は題名だけ見た時は、何ていいかげんな(失礼!)と思ったのだが、原題も「ヒトラーVSピカソとその他」というものだった。
ナチスの美学は「キッチュ」だといわれる。辞書には「紛い物」とあるが、要するに小市民が上流に憧れる“美的な成り上がり”趣味のこと。つまりは芸術における俗物根性なのだ。
このキッチュがナチ時代に限らず、現代の大衆文化全体に関わっていることを明確に示した有名な美術論が、アメリカの美術評論家クレメント・グリーンバーグ著「アヴァンギャルドとキッチュ」。それを収めた「グリーンバーグ批評選集」(勁草書房 2800円+税)は、今も広く読み継がれている。
<生井英考>