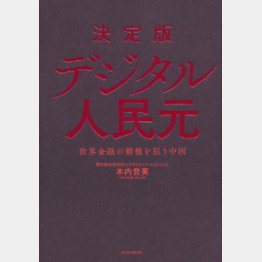デジタルマネー狂騒曲
「決定版 デジタル人民元」木内登英著
日増しに世界に不気味な影を落とす中国の存在感。その背景には当局が推し進めるデジタル通貨の脅威がある。
◇
デジタル通貨とは何か。それが国家の中央銀行が発行する場合、仮想通貨とは違い、法定通貨(貨幣)と同じ法的能力を持つ。中国はこのデジタル化した人民元を昨年10月、深圳市の住民にご祝儀として1人当たり200元ずつ、デジタル人民元を配布した。
その狙いは何か。実はその前、フェイスブックがデジタル通貨「リブラ」を発行すると発表。各国の金融当局はすぐにリブラがマネーロンダリングなどに利用される危険があると強く牽制したが、その前からデジタル通貨を研究してきた中国は、表向き他国と歩調を合わせながら、実は導入計画を前倒しに実証実験を開始したのだ。その狙いは「人民元の国際化」、ひいては国際基軸通貨となっている米ドルの地位を奪うこと。
日銀で審議委員を務めた経歴を持つ野村証券系シンクタンクのエコノミストの著者は、デジタル人民元構想の詳細や米中対立への影響、日本の課題などに広く目を配る。中国は米国に対抗して独自の国際決済制度を構築したいのだが、中国経済は実はドル依存度が高く、そこが大きな弱点となる。グローバル経済の時代は単純な冷戦二元論では語れないのだ。
日本のとるべき戦略も詳しく解説している。
(東洋経済新報社 1870円)
「デジタルマネー戦争」房広治、徳岡晃一郎著
デジタルマネーとは何か。本書はそれぞれ外資系、日系企業で戦略投資や人事などの間接部門などの実務を経験してきた専門家2人が「米中に勝つ」ことをめざす日本企業の未来戦略を説く。
しかしその要諦は、日本企業が「もっと自信を持つだけでよい」という。現状では未分化の「お金のデジタル化」に日本が先駆ければ、1980年代のような強い日本経済が2030年代に蘇ることも十分可能だというのだ。金のデジタル化はキャッシュレス決済から仮想通貨、あるいは中国などが現在進めているデジタル通貨などの広い範囲に及ぶ。逆に言うと、まだ定義の決まってない状態だが、それゆえに日本にも大きなチャンスがあるという。
仮想通貨やブロックチェーンも現状では欠点が多いが、それを好機ととらえることができれば日本企業の底力が発揮されるというわけだ。
「失われた30年」と「第2の敗戦」の轍を踏まないためにも、いまがチャンスなのだ。
(フォレスト出版 1210円)
「カルト化するマネーの新世界」猫組長(菅原潮)著
かつて投資顧問会社でバブルの波に乗ったものの、泡がはじけて大借金。そこで山口組系の組長を頼ったことで自分も裏社会へ。やがて経済ヤクザとしてインサイダー取引などに深く関わったあと、現在は引退して「現場経験の豊富な」評論家として活動中。この驚くべきプロフィルの持ち主が本書の著者。その人が新型コロナ禍は多数の「はき違え」を生んだという。
いまから半世紀前、ニクソン米大統領がドルと金の兌換停止を宣言して以来、マネーの価値は「信用」で支えられた。ところがコロナ禍は「隣人が感染しているかもしれない」という「不信」をもとにソーシャルディスタンスが決められ、しかもリーマン・ショックの教訓から、実体経済を支えるために未曽有の金融緩和が実施された。実体経済=マネーの出口が停止しているところに大量のマネーが流れ込み、あっという間にバブルになった。
これを前にスマホ片手の個人投資家の群れが「ワクチン銘柄」に飛びつき、しょせんばくちに過ぎない暗号資産に狂奔し、巨大ヘッジファンドを「悪の権化」に見立てた集団攻撃まで起こった。
そんな「歪な信用」(=カルト)をめぐるユニークな経済論だ。
(講談社 968円)