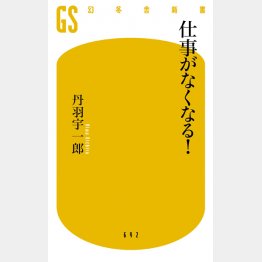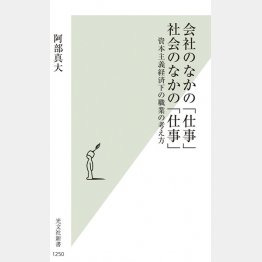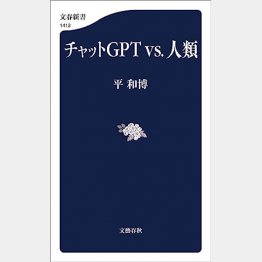AI時代の仕事と社会
「仕事がなくなる!」丹羽宇一郎著
AI時代には人間の居場所がなくなってしまうのではないか。そんな懸念が現実のものになりつつあるという。
◇
「仕事がなくなる!」丹羽宇一郎著
AI時代になるとニンゲンは機械に仕事を奪われ、社会のしくみも人間の常識も変わってしまう--こんな恐怖は、かつてはSF映画だけの話といわれたが、いまや現実になりつつあるかもしれない。現に若手経済学者が政治をAIにまかせるべきだと言い放った極論は少なからぬ反響を呼んだ。
しかし、伊藤忠商事で巨額負債の危機を社長として乗り切った経験を持つ著者はAIに経営判断はできないという。理由は2つ。適切な経営判断は目先の株価だけでなく、商環境の変化、商品の需要、世代別消費、従業員の心理や人間性、技術開発の見通し等々、参考とすべきデータが広範囲で膨大。しかも、AIにどれをどう学習させるかは人間が決めるしかない。
そして、AIが経営判断を誤ったとき、責任は誰がとるのか。そこが問題なのだ。
しかし、他方で著者は従来の日本的大企業経営の時代は既に終わったとも直言。社内副業などギグエコノミーの発想をどしどし取り入れ、「変化する人」に対応できるようなビジネス環境を整えることが大事だと説く。既に80代の著者だが、若々しく柔軟で、しかも大局観を持った人の21世紀論といえよう。
(幻冬舎 990円)
「会社のなかの『仕事』 社会のなかの『仕事』」阿部真大著
「会社のなかの『仕事』 社会のなかの『仕事』」阿部真大著
「やりがい搾取」という言葉は今では広く知られるようになったが、もとは本書の著者がかつて若手社会学者として提起した「自己実現系ワーカホリック」という概念から発展したものだという。本書ではみずから過重労働にハマっていく人間の内面を、より精緻に観察する。
やりがい搾取の内容を子細に検討し、起業してまもない会社にありがちな「お客さまファースト」のマインドが「モンスターカスタマー」を誘発している可能性を指摘。池井戸潤の人気小説に描かれるサラリーマンたちのマインドの分析もなるほどとうなずかされる。
バブル以前の日本と冷戦最末期のソ連を比較し、共通点を指摘するなど面白い試論が目白押しだ。
(光文社 924円)
「チャットGPT VS. 人類」平和博著
「チャットGPT VS. 人類」平和博著
昨年秋、突如としてネット界に登場し、またたく間に世界中を論争に巻き込んだチャットGPT。大学のリポートや会社の企画書などが努力抜きで瞬時に作成されてしまうとあって学校も会社も大騒ぎ。本書は新聞記者から大学教員に転身した著者が、チャットGPTをめぐるメディア上の論争をまとめたリポートだ。
学会論文をチャットGPTで書き、途中で種明かしして威力を実証した英国の例。ネット上に冗談半分で掲載されたフェイクニュースでもチャットGPTの生成AIは事実と受け取って広めてしまう。それを別の生成AIがまた広め……とフェイクの輪が広まっていく話はおそろしい。
ちなみに巻末の参考文献は9割以上がネット発。ジャーナリストの取材まで事実上「非対面」になっているのがわかる。
(文藝春秋 990円)