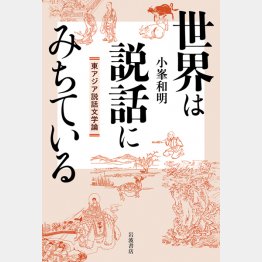「世界は説話にみちている」小峯和明著
「世界は説話にみちている」小峯和明著
ある木匠が龍王の命令で龍宮に出向いて宮殿の造営を手掛ける。龍王は褒美に箱を与え、龍宮のことは決して話してはいけないと言う。地上に戻ると妻たちはもう戻ってこないと葬式を出してしまったが、箱の中には明珠が入っていてそれを売って富を得る。しかし死ぬ間際、妻子に龍宮のことを話すと箱に残っていた明珠は全て消え去った--。
浦島太郎を彷彿させるこの話はベトナムに伝わる説話だ。同様の龍宮から帰還した者の話は、中国、朝鮮半島、カンボジアなど東アジア各地で語り継がれているという。
これまで昔話や説話の研究は日本国内に限られる傾向だったが、近年は広く東アジア世界との比較研究が進んでいる。ことに、日本、中国、朝鮮半島、ベトナムは〈漢字漢文文化圏〉という共有文化がある。漢字漢文を用いないほかの国々でも、仏教文学という共有の文化があり、より広範な形で比較研究が行われるようになった。そうした成果を踏まえながら、東アジアの説話文学世界を紹介したのが本書だ。
前近代の東アジアの世界観のよりどころとなっているのが宇宙の中心にそびえる須弥山。須弥山は仏教の伝来とともにインドから東アジアに広まっていく。天界にそびえる須弥山の対極にあるのが海中の龍宮で、どちらもさまざまな説話の源泉となっている。
もうひとつ共通する説話の源泉として重要なのが、仏教の開祖釈迦の伝記物語。中でも釈迦が出家する契機となる「四門出遊」は日本の古典でも多く取り上げられ、東アジア各地で多くのバリエーションが生まれている。この物語は中東を経てヨーロッパにも伝わり、安土桃山時代の日本には、釈迦がキリスト教徒になるという説話が逆輸入されている。
そのほか、イソップの昔話や人生の無常を説く〈二鼠譬喩譚〉を例に説話の東西交流の具体例を示すなど興味深い話題が盛り込まれ、説話の世界を大きく広げてくれる。 〈狸〉
(岩波書店 3630円)