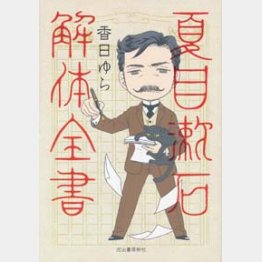夏目漱石特集
「夏目漱石 解体全書」香日ゆら著
2017年は、明治の文豪・夏目漱石の生誕150年にあたる年だ。そこで今年の夏は学生時代を思い出し、漱石作品を手に取ってみてはいかがだろう。今回は漱石の残した数々の名作はもちろん、その人物像にも迫る漱石関連書籍5冊を紹介。大人になってから読む漱石には、新たな発見があるかもしれないぞ。
漫画家であり夏目漱石ファンでもある著者による、漱石ガイドブック。作品だけでなく、人物像やゆかりの地、友人関係などを漫画や写真で紹介している。
漱石の顔といえば旧1000円札の肖像画で誰もが知るところだが、声はどんなふうだったのか。漱石の生徒であり詩人でもある中勘助は、“少し鼻に抜ける金色がかった金属性の声”と表現している。立派なひげをたくわえた顔からは想像しにくいが、高音のキンキンとした声だったのだろうか。
東京には漱石ゆかりのスポットが多い。早稲田駅2番出口を出て早稲田駅前交差点に見えるのが「夏目漱石誕生之地」碑。そこから夏目坂を上って行きつくのが漱石最後の住居があった漱石公園だ。漱石はじめ多くの偉人が眠る雑司ケ谷霊園、正岡子規宛ての手紙の中で「可愛らしい女の子を見た」とつづられた御茶ノ水の井上眼科病院、漱石が万年筆を購入していた日本橋の丸善では漱石愛用の原稿用紙をデザインしたメモ帳が購入できる。
夏休みなどに巡ってみては?(河出書房新社 1300円+税)
「夏目漱石」十川信介著
漱石の作品を、生い立ちや家族構成などの実生活と対比させることで、彼の人物像を読み解いていく。
町方名主の五男として生まれた漱石。長男は家を継ぐ者、次男はその備え、三男以下は他家へ養子に出されるのが一般的だった時代、42歳で漱石を産んだ母は“この年で恥ずかしい”と漏らし、乳児の頃に早々に里子に出してしまったという。
里子に出された塩原家で漱石は溺愛され、玩具などを好きなだけ与えられる。小説「道草」では年頃の子どもと遊んだ記憶がない主人公・健三の様子が描かれるが、これは塩原家での体験だ。
しかし漱石は、のちに塩原姓のまま夏目家に引き取られる。「道草」の中には、「実家の父に取っての健三は、小さな一個の邪魔物であった(中略)殆んど子としての待遇を彼に与えなかった」という一節がある。この強烈な反感を証明するかのように、漱石は16歳で実家を出ている。
妻・鏡子や、友人たちとの関係などにも言及。小説という仮構を通して、人間・漱石の生きざまが見て取れる。(岩波書店 840円+税)
「牛のようにずんずん進め」齋藤孝著
「真面目にやっているのに評価してもらえない」と思ったことはないだろうか。しかし、この「真面目」とはどういうことだろう。その問いに答えるのが、夏目漱石であると本書。漱石は作品の中で真面目という表現をよく使い、その意味を追求しているためだ。
小説「こころ」の中には、「あなたは本当に真面目なんですか。あなたは腹の底から真面目ですか」という一節がある。真面目な学生が、真面目に生きるための教訓を先生に問うたときに返される言葉だ。漱石は、腹の底にあるものを話した時に、相手も腹の底で覚悟を持って受け止めることこそ真の真面目力であると説いている。真面目とは、逃れようもないほど重いものでも受け止める力のことだと。
小説「虞美人草」では、「真面目とはね、君、真剣勝負の意味だよ」ともつづっている。与えられたことをただこなすのが真面目なのではない。常に覚悟を持ち、真剣勝負で物事に挑むことで初めて“自分は真面目”と言えるのだ。
現代人が仕事や人間関係と「真面目」に向き合うヒントを教えてくれる。(草思社 1500円+税)
「漱石と『學鐙』」小山慶太編著
創刊120年を迎えた丸善出版刊行の広報誌「學鐙」の中に掲載された漱石関連の記事から、選りすぐりの25編を収録。
半藤一利の「月給八〇円嘱託教員―漱石の松山行き・探偵メモ」では、漱石が松山中学校に着任していた当時の、実在した教師たちのあだ名などが記されている。もととなるのは、わんぱく中学生たちが教師を揶揄するために作った数え歌。「一つ弘中シッポクさん 二つふくれた豚の腹~」などと続く。
シッポクさんは、卓袱うどんを4杯食ったという伝説を持つ数学教師の弘中又一先生のこと。英語教師の西川忠太郎先生は太った体形からひどいあだ名を付けられているが、「ホホホホ」と格好つけて笑う癖があり、時々赤シャツを着ていたそうだ。ちなみに漱石の数え歌は「七つ夏目の鬼瓦」。鼻のあたりにわずかに残る、疱瘡の痕をわんぱくどもに発見されたゆえと思われる。(丸善出版 1600円+税)
「漱石と日本の近代(上・下)」石原千秋著
漱石作品の主人公には、高い教育を受けながらも無為徒食の者が多い。加えて、自意識が強い一方で他者との関係に自信が持てない者も登場する。彼らはまるで、私たち“現代人”のようだ。
例えば「坊っちゃん」には、さまざまな差別の線が引かれている。自由を得た近代は、“他人とは違う”という差異の線を自ら引くことでしか自分を確認できない時代でもある。そして、差異よりもさらに強い差別という線を引いているのが「坊っちゃん」であり、その差別は近代を強烈に映し出している。何しろ兄を「女の性分」、赤シャツを「女のよう」と形容する女性差別、清を「教養のない婆さん」と呼ぶ学歴差別、生徒を「土百姓」と切り捨てる職業差別など、数え上げればきりがないほどだ。
「三四郎」や「それから」「こころ」などの名作から、近代の資本主義や家族、自由、恋愛などについても読み解いていく本作。私たちを映し出す鏡のような漱石作品が、今も読み継がれている理由が分かるだろう。(新潮社 各1300円+税)