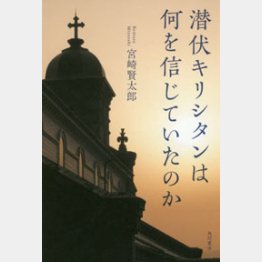神父と隠れキリシタンの再会は粉飾か
「潜伏キリシタンは何を信じていたのか」宮崎賢太郎著/KADOKAWA 1700円+税
一昨年マーティン・スコセッシ監督の映画「沈黙―サイレンス―」(原作・遠藤周作)が公開され、今年には「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」がユネスコの世界遺産に登録される可能性が高いなど、ここにきて潜伏キリシタン(隠れキリシタン)に対する注目が高まっている。我々がイメージする潜伏キリシタンとは、「幕府の厳しい弾圧にも耐え、仏教を隠れみのとして命懸けで信仰を守り通した」というもの。だが、果たしてそうなのか。本書はこうした固定観念に疑義を呈するところから始まる。
江戸初期の1644年、最後の宣教師が殉教し、以後キリスト教の禁教令が解かれる1873年までの230年近く、日本にはひとりも宣教師がいなかった。しかも信徒の多くは領主であるキリシタン大名によって集団改宗させられた一般民衆で、彼らがキリスト教の教義を正確に理解していたとは思えない。指導者もなく教義も知らずにどうやって「信仰」を守り抜くのか。
考えられる答えはひとつ。彼らが信仰していたのは本来のキリスト教とはおよそ違ったものだった。となると、1865年、浦上天主堂でのプチジャン神父と信仰を堅持してきた隠れキリシタン一行との感動的な再会=「信徒発見」にも粉飾が施されていると考えざるを得ない。さらに、禁教令廃止後もカトリック教会に帰属することなく先祖伝来のキリシタン信仰を継続する人たち(カクレキリシタン)が現存している――。
まさに通説を覆すものだが、長年カクレキリシタンのフィールドワークに携わっている著者だけに説得力がある。加えて、なぜ日本ではキリスト教徒が増えないのか(人口比1%未満)という根本的な問題にも迫っている。日本のキリスト教史に新地平を開く刺激的な書。
<狸>