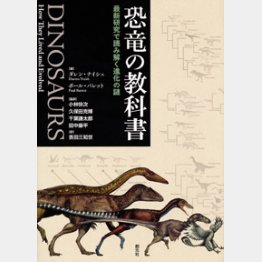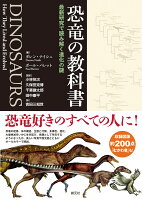「恐竜の教科書」ダレン・ナイシュ、ポール・バレット著、小林快次ほか監訳 吉田三知世訳
現在は人類が我が物顔で暮らしている地球だが、かつてこの星に君臨していたのは恐竜たちだった。約2億3000万年前の三畳紀に出現して以来、約1億6000万年にわたって我が世の春を謳歌した恐竜たちは、6600万年前に絶滅したとされる。
しかし、実は恐竜たちはまだ地球上に生きているという。もちろん映画「ジュラシック・パーク」のような秘密の楽園が存在するわけではない。
その正体は、鳥たちだ。鳥は恐竜の親戚や、子孫とかいうのではなく、「系統樹」上ではれっきとした恐竜の仲間、恐竜そのものだということが数々の化石によって明らかにされているという。
本書は、急速に進む恐竜研究の最新知見も網羅しながら、恐竜についての基礎的知識が学べるカラー入門書。
「非鳥類型恐竜」(鳥類をのぞいたすべての恐竜)と呼ばれる動物のグループが初めて科学的に認識されたのはビクトリア朝時代の1840年代、イギリスの解剖学者リチャード・オーウェンによってだった。
彼は、イギリス南部で見つかった3種類の巨大な爬虫類の化石が他の爬虫類にはない特徴を共有していると主張して、ラテン語で「恐ろしいトカゲ」を意味する「恐竜類」と名付けた。
以降、現在まで膨大な数の化石が発掘・研究され、これまでに1000を超える種が命名されてきた。現在では恐竜の皮膚に生えていた羽毛や繊維、その他の構造について、多くの情報が得られる。筋肉や消化管や他の内臓が残されている化石もあり、技術の進歩と相まって、恐竜研究は数十年前の恐竜像とは全く異なるその実態に迫りつつある。
そんな恐竜研究の歴史に始まり、恐竜の起源や分類、カラダ、生物学、そして絶滅をどのように生き延び、鳥類として進化していったのかまでを詳細に解説。
何よりも読者が興味をそそられるであろう生態と行動についても、コンピューターを用いた「有限要素解析法」などによって、古生物学者の仮説が検証されてきている。
こうした研究から、例えば「アロサウルス」の頭蓋骨は応力によく耐え、その咬合力に必要な耐久性をはるかに超えていることが判明。この発見によって、アロサウルスは狩りの際に、頭部全体を手斧のような武器として使っていたのではないかという説がより説得力を得たという。
その他、長年論争が続いている恐竜は内温性か外温性かという論議、巨体と特異な体形ゆえに謎が多い交尾や繁殖戦略、子育てなど。迫力ある恐竜たちの復元イラストレーションや化石の写真など、多くの図版を駆使しながら、解き明かしていく。
子供向けの恐竜本だけでは物足りなかった恐竜好きの大人たちの知的好奇心を満足させてくれる豪華な「教科書」だ。
(創元社 4500円+税)