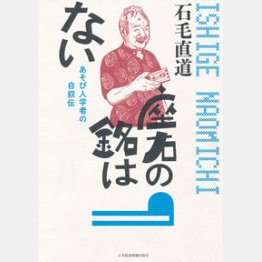「座右の銘はない」石毛直道著
発掘、探検、辺境への旅……。少年時代そのままにワクワクすることをやり続けた文化人類学者のケタ外れの半生記。
トンガ、タンザニア、ニューギニア、リビアなど、辺境の地でフィールドワークを行い、小さな動物園ができるほど、いろんな生き物を食べた。食中毒にも肝炎にもなった。体当たりの学術探検を経て食文化の研究を始め、先駆的な業績を残した。
1937年、千葉市生まれ。子ども時代に戦中・戦後の激しい飢餓を経験した後遺症か、大食いになった。やがて考古学に興味を持ち、海外での考古学的探検に憧れて、京都大学へ。探検部に入部し、辺境の地で鍛えられた。探検部の顧問には今西錦司、梅棹忠夫、中尾佐助ら、知の巨人たちが名を連ねていた。座して学ぶ学者たちではない。酒があれば談論風発。自由闊達な気風があった。
大学院中退後、京都大学人文科学研究所に採用され、梅棹忠夫の助手となる。自炊生活とへき地での食経験から発想した「でたらめ料理」が人気を呼び、研究室でクッキングスクールまで開いてしまった。
「おもろい」ことをやり続けているうちに、考古学から文化人類学へ、そして食文化の研究へと、的が絞られていった。結婚前、飲み屋へのツケを清算しようと書いたエッセー「食生活を探検する」が注目されたが、「学問の正道を踏み外している」と心配する人もいた。食について論じるなど学問ではなく、遊びと思われていたからだ。しかしその後、魚介類の発酵食品の研究、世界の麺のルーツを探る研究などで食文化研究を牽引し、多くの業績を残した。管理職は嫌いと言いつつ、国立民族学博物館の3代目館長も務めた。
多忙な職務から解放されてからは個人事務所を設立。80歳を過ぎたいま、書きたいことを書き、電動自転車で大好きなスーパー銭湯に通う日々だという。梁塵秘抄の「遊びをせんとや生まれけむ」そのものの人生を楽しんでいる。
(日本経済新聞出版社 1800円+税)