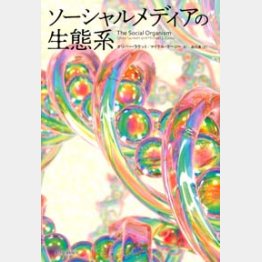生き物としてのIT
「ソーシャルメディアの生態系」オリバー・ラケット、マイケル・ケーシー著 森内薫訳
確実に世界と時代を変えたIT(情報技術)。最近はネットを「生物」と考える議論も登場した。
◇
炎上やらヘイトが跋扈するSNSの世界。分別あるはずの高齢者までもがたやすく嫌韓嫌中に走ったかと思えば、香港のデモのように市民の自発的な蜂起を促したりもする。
ソーシャルメディアは「コミュニケーションを加速させる感情的なトリガー」を備え、あらゆる人々が「自由のための強力な道具」とみなしている。だが、その「自由」はテロ組織にも共有されているのだ。
本書は米ディズニー社のイノベーション部門のトップをつとめる「テクノロジー・アントレプレナー」が“生命体としてのソーシャルメディア”の可能性を語る。
SNSがヘイトの書き込みであふれかえっている現実は困りもの。しかし著者は書き込みの検閲には明白に反対。検閲は抗生物質と同じ。薬に頼ってばかりいると、生き物であるSNSはいつまでも自律的に免疫力を獲得できないという。
もうひとつはブロックチェーン技術の進化によって、海賊版の防止から少額決済の実現までが可能になること。仮想通貨のトラブルなどもあるが、理論的に見て最も信頼度の高いシステム。これに基づいて収益性を高めることは社会の安定化に確実につながるという。
(東洋経済新報社 2200円+税)
「機械翻訳と未来社会」瀧田寧、西島佑編著
外国人旅行者の急増で、飲食店ではポケトークがバカ売れという。だが、機械翻訳は本当に言葉の壁をなくすのか。本書は理系の研究者たちが論じることの多かった「機械翻訳」を文系の側から考えるユニークな試みだ。
この数年で機械翻訳の精度が一気に上がったのは深層学習のたまもの。しかし深層学習は既存の社会をそっくりなぞるだけ。機械翻訳が「言葉の壁」をなくすわけではなく、英語優位の現状はいっこうに変わらない。では機械翻訳はだめなのか。そこから先が本書の面白さ。哲学、文学、言語学の研究者たちが集まったユニークな論集。
(社会評論社 2000円+税)
「僕らはSNSでモノを買う」飯高悠太著
最近目立って増えたのがSNSを使ったマーケティングの指南書。本書は10年以上前からSNSの可能性に注目してきた著者によるSNSマーケティングの極意だ。
著者のキーワードはUGCとULSSAS。前者は「ユーザー・ジェネレーテッド・コンテンツ」の略で「ユーザーが自分の意思でつくるコンテンツ」のこと。要はSNSで発信したり、リツイートしたりする投稿のことを「コンテンツ」と呼んでいるのだ。このユーザー投稿に「いいね」(Like)を押し、そこに記されたブランドや企業名を、まずSNSで探し(サーチ1)、次にグーグルなどのブラウザーで探し(サーチ2)、実際に買ったり探したりして(アクション)、その感想を拡散(スプレッド)するのがULSSAS。なんだ、いつもやってることじゃないかというのがミソ。いま誰もが無意識にやっていることを改めて意識化することで、SNSという生き物をうまくのりこなすことができるのだ。
(ディスカヴァー・トゥエンティワン 1500円+税)