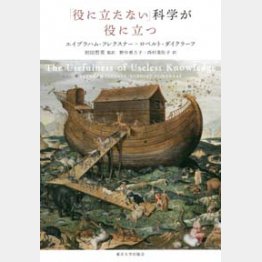「『役に立たない』科学が役に立つ」エイブラハム・フレクスナーほか著 初田哲男監訳 野中香方子ほか訳
基礎科学とは、真理の探究そのものが目的とされ、応用化学のようにすぐには「役に立たない」が、長期的な社会課題の解決や新産業の創出に欠かせないものだ。
本書はプリンストン高等研究所の現所長、ダイクラーフの「明日の世界」と初代所長フレクスナーの「役に立たない知識の有用性」の2つのエッセーを収め、基礎科学研究の有用性を説いている。
1933年に開設されたプリンストン高等研究所は、世界中から第一線の学者を集め自由な研究をさせたが、ことに物理学・数学の分野は群を抜き、アインシュタイン、フォン・ノイマン、ゲーデル、チューリングら超一流学者が在籍していた。
同研究所の基礎研究から生まれた代表的なものに原爆とコンピューターがある。アインシュタインの相対性理論が発表されたのは1905年だが、その当時これがどう「役に立つ」かは皆目見当がつかなかった。たとえば現在のモバイル社会に必須のGPSも、相対性理論があったからこそ位置特定に誤差を生じずにすんだとダイクラーフは言う。
また、フレクスナーは(1930年代末の世界において)最も有益な人物は誰かとフィルムを発明したイーストマン・コダックに質問したところ、無線電信の開発者、マルコーニという答えが返ってきた。それに対してフレクスナーは、マルコーニのような人物はいずれ出てきたろうが、電磁波の理論と検出・実証をしたマックスウェルとヘルツこそが真に有益な人物だといって、基礎研究の重要性を示した。
本書で繰り返し述べられているのは、我々が現在享受しているイノベーションのほとんどは、役に立つ、役に立たないとは無関係に、ひたすら真理を探究したいという基礎研究から生まれたものだということだ。その場合、何より重要なのは「精神と知性の自由」であり、「人類の真の敵は、人間の精神を型にはめ、翼を広げさせないような人々」だというこのフレクスナーの言葉を、学術会議という学問の自由な領域を侵そうとしている現首相に捧げたい。 <狸>
(東京大学出版会 2200円+税)