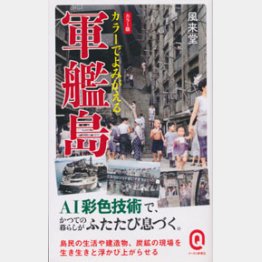「カラーでよみがえる軍艦島」風来堂著
2015年に世界文化遺産に登録された通称「軍艦島」、正式名「端島」は1974年に海底炭鉱が閉山、無人化してから約半世紀。現在では廃虚の島として人気を集め、上陸ツアーなども催されている。
廃虚化ゆえか、現代人にはモノトーンのイメージしか浮かばない軍艦島だが、かつては住人たちの暮らしがあった。
本書は、当時のモノクロ写真にAIによるカラー再現処理をほどこし紹介しながら、そんな軍艦島の歴史を振り返り、最盛期の賑わいや往時の住人たちの日常などを伝えるビジュアル新書。
端島で石炭が発見されたのは江戸時代の1810年ごろとされるが、本格的に採炭事業が始まったのは、1890(明治23)年に石炭需要を見越した三菱が買収、その経営下に置かれた後のことだ。
もともとは、現在の3分の1ほどの小さな島だったが、採炭時に生じる不要な岩石や廃石を用いて大規模な埋め立てを実施、外海に面した西側に住人たちのアパート群や各種の生活施設、内海に面した南東部に採炭設備が整えられていった。
不純物の含有率が低く、日本一の品質と評価されていた端島の石炭は、明治から大正期はツルハシを用いて人力で壁を削る「手掘り」だったが、昭和10~20年代には小型の手持ち採炭機、そして昭和30年代には大型機械が導入され効率が飛躍的に向上。並行して運搬や換気、排水、事故防止のための周辺設備も整えられ、「地底の大工場」と呼ばれるほどに発展した。
そうした炭鉱としての発展史を、坑内の作業風景を撮影した写真とともにたどる。
狭い坑道で機械を満載した台車を押す作業員や入坑のため竪坑内を上下するケージに乗り込む採炭員など、時の経過を感じさせないリアルな写真で当時の様子が蘇る。
大正時代に入ると、日本最古の高層鉄筋コンクリート(RC)造アパートが建ち、ピーク時の1959年には総人口5300人、1平方キロ当たり当時の東京の18倍という世界一の人口密度となった。
後半は、そうした住人たちの暮らしぶりに迫る。住宅は基本的に社宅のため無料、水道光熱費もすべて合わせて10円(昭和34年)、一方で新卒の初任給が5万~6万だった昭和47年時に月給が約20万円と、島の生活は極めて恵まれたものだったという。
電化もいち早く進み、庶民の憧れの三種の神器「テレビ・洗濯機・冷蔵庫」の全国普及率が数%から20%だった時代に、島では保有率がほぼ100%だったそうだ。
飲食店や商店も充実、おまけに目抜き通りには連日のように島外からやってきた行商人による青空市も開かれ、一時期は遊郭まであったという。
そんな当時の賑わいから、海水を利用したプールや運動会など、娯楽の様子まで写真で振り返る。
往時を知る当時の住人たちへのインタビューなども併録され、貴重な史料にもなるお薦め本。
(イースト・プレス 1100円)