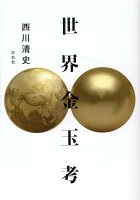「世界金玉考」西川清史氏
なぜ、こんな危険地帯にデリケートなモノをぶら下げているんだ! 男性諸君なら誰しも、鈍痛に悶えながらもキンタマのことを恨んだ経験があるだろう。
「進化の過程で、体内にあった精巣をわざわざ外に出したのがキンタマなんです。今から約1億4600万年前に、哺乳類は2つのグループに分かれました。一番初めにキンタマができたのは、カンガルーとかコアラの祖先の有袋類のグループ。彼らはペニスの前にキンタマがあって、位置関係が我々と逆なんですよ。そこから約5000万年経って我々の祖先の有胎盤類にもキンタマが生まれた。しかし、同じ有胎盤類でも、ゾウやモグラ、クジラやハリネズミなんかはキンタマが見当たらない。なんと彼らは、一度体外に出したキンタマを、再び体内に戻したということなんです」
本書は、生物学、歴史、文学、食に至るまで、さまざまな角度からくまなく光を照らし、ときには体当たりでキンタマと格闘して編さんした、いわばキンタマの総合誌だ。
危険を冒してまで見せびらかすような位置にある男性のキーポイント。ゾウのように紳士的におさめないのはなぜなのか。
「実は、メスに対する性的シグナルとして見せつけているという説があります。でも、ほとんどの陰嚢は地味な色で、目立たないではないかという反論もある。広く言われているのは、精子の生産にとって体内は熱すぎるため、外に配置したという冷却仮説です。しかし、学者からしたら順序は逆で、体外に出してから、低い温度でも精巣がよく働くように進化したという反論があるんですよ。ほかにも、全力疾走仮説やトレーニング仮説など、諸説あるんですけど、実のところまだよくわかっていないんです」
また、著者は世界各国でキンタマがどのように呼ばれているかを調査。英語や中国語、さらにはチェコ語などの8カ国語を母語話者に直接会って聞いて回った。
「英語のようなメジャーな言語は調べられるんですが、マイナーな言語は探しようがないんですよ。しかも、こっちが知りたいのは医学用語の睾丸ではなくて、俗語のキンタマですから、直接会って聞いて回るしかなかったんです。レストランのネパール人にナプキンにイラストを描いて尋ねたら、変態だと思われて無視されてしまって、あれは恥をかきました」
キンタマのことをマレーシア語では「家宝」、フランス語では「奨学金」、フィンランド語では「鈴」と表現。チェコ語に至っては「ゼレンスキーのキンタマは世界一大きい(ゼレンスキーは世界一勇敢な男だ)」という用法がある、などの貴重な話を紹介する。
「面白かったのは、どの国も卵や球体を意味する言葉をよく使うんですね。日本語のキンタマも球体ですよね。一方で、古代の日本では『ふぐり』と呼んでいました。意味は『ふくれる』。卵でも球体でもなかったんです」
最終章ではついに、浅草の居酒屋で、珍味「ブタのきゃん玉刺」を自身の口で味わった。
「ほんとうにまずかった。あれは食べるものじゃない。食感としては硬めの木綿豆腐みたいな感じなんですけど、とにかく味がない。でも不思議なのは、ずっと口の中で噛み続けてジュース状になってから飲み込むと、鼻の中にほんのり麝香みたいな香りがするんです。何度やってもたしかにする。一緒に同席したやつは、しないって言うんですけど」
ゼレンスキーほどの大きなキンタマの持ち主はぜひ、味わってみてほしい。
(左右社 1980円)
▽西川清史(にしかわ・きよし)1952年生まれ。上智大学外国語学部フランス語学科を卒業後、文藝春秋に入社。雑誌畑を歩み、2018年、副社長で退社。著書に「うんちの行方」「文豪と印影」「にゃんこ四字熟語辞典」など。