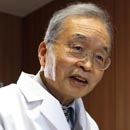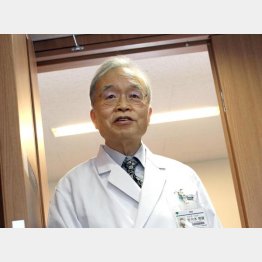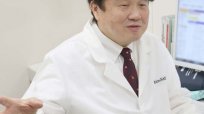意識はなくても「生きている喜びがある」状態は存在する
主婦のMさん(60歳)は、定年を迎えた夫のFさんと娘さんの3人で暮らしていました。5年前の暑い夏に、目まいを感じたのが脳腫瘍との闘いの始まりでした。
がんは大脳の広い範囲に及んでいて、手術では取りきれずに放射線治療が行われました。しばらくは小康を保っていたのですが、2年後の12月の寒い日に高熱を出し、その後、意識を失いました。病院に運ばれ熱は下がったのですが、意識は戻りません。経管栄養が始められましたが、体位を変える時に少し表情が変わったように見える以外は、まったく無表情のままでした。
家族は、主治医から「出血とがんの再発で、もう意識が戻ることはない。長くもっても6カ月くらい」と告げられました。それから2カ月が過ぎた頃、Mさんは勧められた郊外の小さな病院に転院しました。自宅からは遠くなりましたが、病室の外は林になっていて自然に囲まれています。Fさんと娘さんは交代で見舞いに通いました。
Fさんは覚悟していましたが、「一度はまた意識が戻ってくれないか」という期待も抱いていました。しかし、少しでも長く生きて欲しいと思う一方で、時には「意識が戻らないなら、このまま生きていることは幸せなのだろうか?」と考えたり、ある人から「意識がなく、経管栄養で生かされては生きている意味がない」と言われたのを思い出したりもしました。