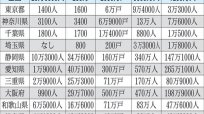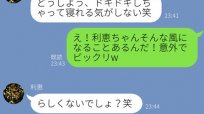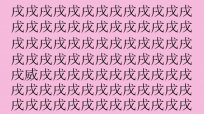維新の前原共同代表が「大学無償化」にも積極発言…定員割れ大学も対象に?格差是正になるのか
多子授業料無償制度の拡充を
制度設計の前提として、今後予想される職業社会での大学などの役割をどう考えるかが大事だ。
文系学部生のホワイトカラーなどがメインで携わっているような仕事は、AIの進展などで着実に減るだろう。半面、福祉・介護などのエッセンシャルワーカーや地域交通や流通などを支える地域社会の働き手の仕事は確実に増えていく。その場合でも介護ロボットや自動運転などAIに関する知識は要求されるようになる。
大学という形態でなくても、そのような専門的な職業人も対象にした高等教育機関も無償化の対象にすべきであろう。
また医学部で最近増えてきた、たとえば卒業後に群馬県内の医療機関で一定期間勤務すれば奨学金の返還が免除されるような地域枠の入試を、医学部だけでなく地方大学の教員養成学部に拡大し、教員不足に備えることも考えられる。これらは東京一極集中に対する対策にもなるだろう。
さらに全般的に一般家庭の大学を含む高等教育機関への就学援助として、現行の多子世帯への授業料等無償化の拡充が考えるべきだ。この「高等教育の修学支援新制度」は、2025年から子ども(中・高・大学生)を3人以上同時に扶養し ている間、所得制限なく、国が定める一定の額まで大学等の授業料・入学金を無償とする制度だ。対象となる大学などは、一定の要件を満たすことが確認された大学、短期大学、高等専門学校(4.5年生)、専門学校となっている。
この現行の制度を、扶養対象の3人から2人に減らして、対象となる高等教育機関の確認条件を厳しくすることによって修学支援の対象を厳選する一方、大学などの努力目標をはっきりさせることができる。
一人っ子家庭で進学困難のケースでは、日本学生支援機構の返済不要な給付型奨学金の拡充で対応すべきである。
このように制度設計は複雑となり、ただ選挙のために一律に「大学無償化」をスローガンに掲げるときのようには理解が得られにくいかもしれないが、日本の現状と課題を考えると検討してみてもいいはずだ。(教育ジャーナリスト/木村誠)
◇ ◇ ◇
いまやキャリア官僚を輩出する大学は東大じゃない?●関連記事【こちらも読む】キャリア官僚がエリートだった時代は終わり…立命館大学が合格者数3位の大躍進…に詳しい。