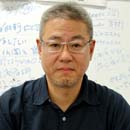「関西で飲もう」太田和彦著
この文庫は関西のグルメ誌「あまから手帖」の連載であり、大阪・京都・神戸の「居酒屋」「割烹」「バー」と、それぞれ約1年間の連載を集めて一冊にしている。
太田和彦さんは居酒屋の本を何十冊も書いているが、この文庫では居酒屋とは少し趣の違う高級割烹、「さか本」「弧柳」「■川」「たん熊北店」など、大阪・京都の超実力店を訪ね、丹念に食べ飲みして、まさにその実況中継を書いている。
大正時代末期に大阪に登場した割烹は、カウンターをはさんで客が料理人と差し向かいで対面しながら、料理をいただくスタイルだ。
料理人は客の前で魚をさばき、刺し身を引いたり、さまざまな食材を煮たり焼いたりするのだが、料理や酒以前の位置に会話のやりとりがあって、それがその日その時のすべてを左右する。
だから、その店の持ち味をよく知る馴染み客にアドバンテージがある。また板前は長い付き合いから、常連客の好みをよく知っているので、客と料理人は「掛け合い」のようなコミュニケーションで、共犯関係のように「おいしい」に肉薄していく。
それにしてもほとんど一見客であるはずの太田さん、店からの愛され方は読んでいて「すごいなあ」と声が出る。うまいものを出してもらう、いわば名人の技芸。
<「要研究だな」ともう一杯手酌するのでした>(「一陽」)
<私は実感した、割烹は楽しい。これだな>(「味菜」)
<最もスタンダードな割烹は自分をワンランク上げてくれたような気がした>(「たん熊北店」)
というような「気持ち良い」姿勢が、手だれの料理人に真っすぐ伝わっているのだろう。
巻末の「おわりに」で、居酒屋編から割烹編に突入する際に、
<「敷居も値段も高い割烹はお決まりのコースをいただく所で(中略)むしろ本当の酒飲みはそんなところに行かない、割烹なんかに出入りしたら「居酒屋の巨匠(本人豪語)」の名がすたる>
と書いているが、太田さんにそういう上方文化の誤謬を刷り込んだのは一体誰だ!(でもやっぱり値段は高いが)。(小学館 510円+税)