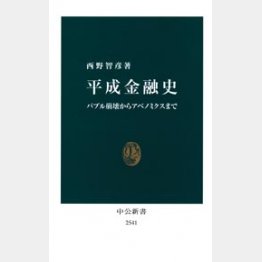追憶の平成バブル
「平成金融史」 西野智彦著
平成の30年間はバブル絶頂から転落の時代。その時代の歓喜と悲惨を振り返る。
◇
平成元年の1989年はバブル絶頂期。自粛ムードをものともせず日経平均は年初に500円近く上げて史上最高値を更新。熱気に沈静化の気配はなく、もう一段の高みを目指し膨張を続けていた。本書は関係者の証言をまじえたドキュメンタリータッチでバブルから転落してゆく日本社会の様相を描き出す。
90年、株価暴落でバブル崩壊が始まるが、折からバブル退治の引き締め策を進めていた日銀は態度を変えず、他方で地価の上昇は止まらなかった。91年、富士銀、興銀などの主力行で次々に不正が発覚。92年には土地バブルも破綻するが、大蔵省と宮沢首相、そして日銀の足並みはそろわず、躊躇と先送りが重なって「失われた30年」の序曲を奏でてゆく……。
著者は民放テレビのベテラン報道プロデューサー。バブルとその崩壊を目の当たりにした世代ならではの迫真性で読ませる。
(中央公論新社 920円+税)
「平成経済 衰退の本質」金子勝著
1987年のブラックマンデー。97年の東アジア通貨危機。2007年のパリバ・ショックと為替市場暴落、そして08年のリーマン・ショック。10年ごとに起こってきたのがバブル崩壊だ。これを著者は「バブル循環」と呼ぶ。ふりかえれば発端は米ドルの金本位制を廃止した71年。それ以降、「管理通貨」の名のもとで「紙幣本位制」とでもいうべき制度が発足。しかしこれは実物経済との関係を断ち切り、通貨発行量に歯止めがなくなる懸念を招く。つまりこれがバブル依存症の元凶だったのだ。
本紙連載「天下の逆襲」でおなじみの著者は歯に衣着せず、平成の財政を真っ向から批判し、今後の教訓を説いている。
(岩波書店 820円+税)
「バブル」 永野健二著
副題にズバリ、「日本迷走の原点1980―1989」。本書は平成の前、昭和の最後の10年に注目しながら、さらにその前から筆を起こすことで日本の戦後経済の歩みを総括する。
日本初の敵対的M&Aでのし上がりながら石油ショックで破綻に追い込まれた三光汽船。81年に登場したレーガン政権によるレーガノミクスの押し付け。85年のプラザ合意はバブル開始の号砲となり、企業、銀行、庶民の発想までが急激に変化してゆく。
アベノミクスを誇る安倍首相のスピーチを聞きながら「危ないな」と直感する著者は元日経新聞のベテラン。「40年間経済記者として市場経済を見続けてきた私の信念」に基づいて、市場をコントロールできると安易に語る政権の姿勢に疑問を呈するのだ。
(新潮社 590円+税)