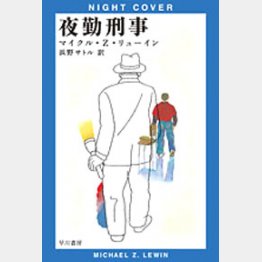画面にあふれる空気はまぎれもなく70年代
「ケリー・ライカートの映画たち 漂流のアメリカ」
外国の友人に「東京ほど映画に恵まれてる街はないね」と言われたことがある。話題の娯楽大作はむろん、ヨーロッパ系や邦画専門の名画座、アート系のミニシアター、映画アーカイブまで、多様な映画を街中でやってる。こんな街はパリを除いてほかにないというのだ。
そんな言葉を裏書きする企画が来週末、都内で始まる「ケリー・ライカートの映画たち 漂流のアメリカ」。
一般の知名度はないが、ライカートはベテランのインディペンデント作家で映画祭でも常連。今回はデビュー作の「リバー・オブ・グラス」(94年)から西部劇の「ミークス・カットオフ」(10年)までの4作が並ぶという。
中でも筆者が心引かれるのが「ウェンディ&ルーシー」(08年)。行方不明の愛犬を必死で捜すという、犬好きの気持ちをギュッとつかむ筋立てのためばかりではありません(笑い)。現代のアメリカ映画に失われた“70年代の匂い”のあるライカート作品らしさが特に顕著だからだ。
ラディカル革命の60年代とレーガン保守革命の80年代に挟まれた70年代はアメリカの失意の時代。映画界ではコッポラやスピルバーグも登場したが、ペキンパーの「ガルシアの首」や「ダーティハリー」シリーズ、そしてハリウッドで役者業をこなしつつインディーズ映画界の確立に尽力したジョン・カサベテスの「こわれゆく女」が70年代。住所不定の流れ者の話という点で最近話題の「ノマドランド」の先駆ともされる「ウェンディ&ルーシー」だが、画面にあふれる空気はまぎれもなく70年代を知る世代のものなのだ。
そういえばハードボイルド小説も70年代はトーンが違う。M・Z・リューインの人気シリーズ第1作「夜勤刑事」(早川書房 1012円)もまさに70年代らしい文体が持ち味である。 <生井英考>