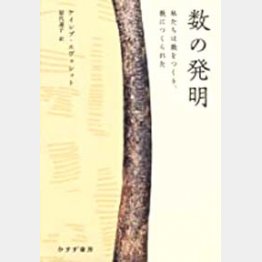「数の発明」ケイレブ・エヴェレット著 屋代通子訳
認知症のテストに、自分の年齢を言ったり、100から順に7を引いていくものがあるが、このテストには「数」という概念が既知であるとの前提が必要だ。しかし、著者が幼少期を過ごしたアマゾンには数を持たない先住民族がいる。それでも彼らは不自由なく暮らしてきた。つまり、数という概念は人類に先天的に備わっていたものではなく、車輪や電球と同じく「発明」されたものだということだ。
本書は、人類が数というものをいつ、どうやって認識・発明したのかを、言語人類学者である著者が、言語学、認知科学、考古学、生物学、神経科学、動物行動学など広範な視点から解き明かしていく。世界各地の数の体系はおよそ7000の言語に及んでいるが、その大半は5や10を単位にしている。これは数を数えるときに指を折るという共通のしぐさから来ており、5本の指、あるいは両手を広げた10本の指が基本となっている。
また、どの言語も1、2、3までは正確に区別しようとするが、それより多い量となるとかなり大ざっぱな言い方をするものも多い。これは我々ホモサピエンスの脳が小さな数だけを正確に識別するようにあらかじめ装備されていて、それ以上の量はアバウトな類推として扱うことに起因している。現に、先のアマゾンの先住民は2より大きな量を正確に表す単語がなく、オーストラリア諸言語でもその多くは3か4が最大の数量で、おおむね上限は10未満だという。大きな数量を表す言葉がない(必要としない)これらの民族に共通するのは、狩猟採集をその文化の基礎としていることだ。
それに比して、肥沃(ひよく)なナイル川の農業大国エジプトのピラミッドは数や数学がなければ建設することができない。逆にいえば、農耕文化こそこの数の体系の生みの親であり、桁の大きな数を見いだしていかなければ農業革命は起こりえなかったということだ。
数を数えるというごく当たり前の行為の背景にある広大な世界を、豊富な実例とエピソードと共に開示してくれる。知的刺激に富む一冊。 <狸>
(みすず書房 3740円)