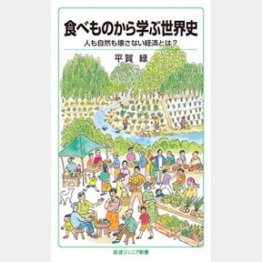「食べものから学ぶ世界史」平賀緑著
先頃、国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が産業革命前と比べた世界の気温上昇が、これまでの予測より10年早く2021~40年に1・5度に達すると予測、人間活動の温暖化への影響は「疑う余地がない」と断定した。現在の農業と食料システムではかなりの温室効果ガスを排出しており、地球温暖化の一大要因になっている。世界には120億人を養うのに十分な食料があるというのに、現在78億人いる世界人口のうち、慢性的な栄養不良の状態に陥った飢餓人口は7億~8億人、20億人が食料不安に直面している。
この明らかな矛盾はお金で計れる部分だけの効率性や成長のみを目指す資本主義というシステムに起因している、と著者はいう。つまり、現在起きている気候危機も格差社会も貧困問題も「資本主義のシステムとしてはその目的通り真っ当に機能している結果」なのだと。本書は砂糖、小麦、トウモロコシ、豚肉などの身近な食べものを通して資本主義経済の歴史とカラクリを紹介したもの。
ヨーロッパでは17世紀半ばまで王侯貴族が薬としてわずかに口にできるぜいたく品であった砂糖が19世紀半ばには労働者たちの日常的な食事にまでなった。これはサトウキビが育つ熱帯地方の植民地にサトウキビだけを大量に生産するプランテーションを築き、現地人や黒人奴隷などの安価な労働力を使って「商品」として大量に生産したからだ。その結果、現地人は自分たちに必要な農産物を生産できなくなり、単一栽培によって土地は痩せ環境破壊を引き起こす。綿花、小麦、トウモロコシなども同様で、ひたすら効率の良い「商品」として大量生産されていく。
しかし、作りすぎれば値崩れを起こしてしまう。では余剰物をどうするか。戦後日本の給食でパンが主食になったり、インスタントラーメンが普及したのは米国産の余剰小麦がもたらしたものだと指摘されると、うなずける。気候危機も飢餓も待ったなしの現在、資本主義一辺倒の経済システムからの脱却は必至。本書はその良き道案内となっている。 <狸>
(岩波書店 902円)