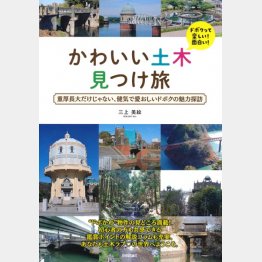「かわいい土木見つけ旅」三上美絵著
「かわいい土木見つけ旅」三上美絵著
全国各地の「古くて、小さくて、人々に愛され、大切にされている」土木構造物=土木を巡り、その魅力を伝えるビジュアル探訪記。
「土木」と「かわいい」の組み合わせに違和感を抱く読者も、これを見ればすぐに納得することだろう。
JR水戸駅から車で9分。水戸城跡の高台に立つ「水戸市水道低区配水塔」だ。
高さ約22メートル、直径約11メートルの円筒形の建物は、屋根が丸みを帯びたドームになっており、建物の真ん中に配されたバルコニー風の回廊は上下が空色とクリーム色のパステルカラーで塗り分けられている。正面や丸窓・長窓の周囲は繊細なレリーフで飾られており、まるでテーマパークに紛れ込んだかのようなメルヘンチックな建物で、今から90年以上も前の1932年に建設されたとは思えない。
建物の中には、小学校のプール1つ分ほどの水をためられる水槽があり、各戸へ供給していた(1999年まで現役で稼働)。
名称に低区とついていることから分かる通り、かつては「高区」もあった。同時期に建設された「高区配水塔」は鉄骨の櫓の上にむき出しの水槽をのせただけのそっけないデザインで、低区塔も当初の図面では今ほどの優美な姿ではなかったという。
それがなぜ、このようなラブリーな外観になったのか、著者は歴史をひもといていく。
一方、1933年竣工の埼玉県行田市の「堀切橋」誕生の遠因は、あの徳川家康までさかのぼるという。家康は、頻発する洪水から江戸を守るために、合流して東京湾にそそぐ荒川と利根川を分離する大胆な瀬替え事業を実施。結果、切り離された荒川の本流「元荒川」の支流沿いの農村が用水不足となり、大正末から昭和初期にかけて行われた改修工事で誕生したのが、この堀切橋なのだという。
橋長20メートルにも満たない小さな橋なのだが、高欄(欄干)は独特の意匠で、中柱や親柱にも不思議な形の装飾がついている。そのデザインが評価され、土木学会の「選奨土木遺産」にも選ばれているそうだ。
瀬戸内海の小さな無人島に立つ鍋島灯台(香川県)は1872年の創建時の姿がほぼ残る。灯台が未整備だった当時、瀬戸内海は海の難所で、この鍋島灯台は「夜間に無理な航行を促すより、安全な場所に停泊させて夜が明けてから難所を通す」ために船がその先へ進まないようにする「停泊信号」として使われた珍しい灯台だという。
こうした「とにかく愛らしい!」と著者イチ押しのドボクから、東京都板橋区の住宅街の突き当たりに設けられたロータリー形式の転回スペース「クルドサック」など、見逃してしまいそうな「身近にあるドボク」や、農業用の灌漑用水を正確な比率で分配するための装置「久地円筒分水」(神奈川県川崎市)など、人々の悩み事を解決した「生活を変えたドボク」まで41物件を紹介。
ドボク愛に満ちたコラムも充実。一読すれば、きっと周囲のドボクも以前とは違って見えてくることだろう。
(技術評論社 2420円)