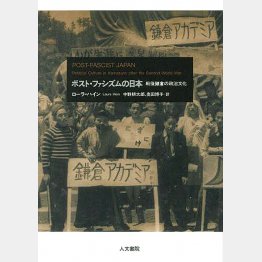「ポスト・ファシズムの日本」ローラ・ハイン著 中野耕太郎、奥田博子訳
「ポスト・ファシズムの日本」ローラ・ハイン著 中野耕太郎、奥田博子訳
敗戦直後、静岡県三島市に開設された庶民大学三島教室(三島庶民大学)に講師の一人として参加した若き丸山眞男は、狭い教室いっぱいにさまざまな層の人たちが集まり、知的飢餓に陥っていた人たちの熱気が伝わってきたと語っている。こうした庶民に向けての公開講座は三島だけでなく、京都の京都人文学園、長野の上田自由大学、鎌倉の鎌倉アカデミアなど各地で行われていた。
戦時中に制限されていた知的好奇心を満たしたいという人たちの欲望と、心ならずも戦争に協力してしまった知識人たちの悔恨とが相まって成り立ったもので、ここから多様で民主的な実践が生まれていった。本書は、鎌倉という街をモデルに、地方自治体の知識人と市民とが一体となってポスト・ファシズムの時代にいかに民主主義を構築・定着させていったかを跡づけたもの。
著者はまず久米正雄、大森義太郎、大佛次郎といった文化人たちによって形成された文化都市としての面、東京からほどよい距離にあるリゾートという特質に焦点を当てる。次に、戦後の人文教育の場として大きな影響を与えた鎌倉アカデミアについて概観する。学長の三枝博音をはじめ、林達夫、高見順、吉野秀雄、服部之総、千田是也、村山知義らの講師陣を揃え、山口瞳、いずみたく、前田武彦といった卒業生を輩出した。
もうひとつの拠点が土方定一が館長を務めた神奈川県立近代美術館だ。同館はその後の地方美術館の管理運営のモデルとなるが、それは都市行政としての美術館という機能をいち早く打ち出したからだが、それを支えたのが正木千冬市長らの行政だった。
内外問わず多くの観光客であふれる鎌倉だが、ここへ至るまでには多くの人たちの試行錯誤の積み重ねがあり、ファシズムという嵐の時代を繰り返さないためには国家ではなく、地方自治体が市民と一体となって独自の機能を築いていくことがいかに大事かを教えてくれる。 〈狸〉
(人文書院 4950円)