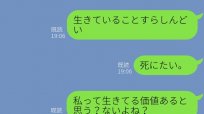多様性に富んだまちづくりと喫煙規制(下)「喫煙者を公園から排除するのではなく共生できる環境づくりをすべき」
溝口の再開発エリアなど公共施設、空間における分煙環境推進の取り組みを行ってきた市議会議員の大島明氏(自民)に、今回の市の施策について聞いてみた。
「老若男女不特定多数の人々が憩いの場として利用している公園だからこそ、喫煙者、非喫煙者が共生できる環境が必要です。たばこは合法的な嗜好品です。喫煙所の設置は当たり前のこと。(18カ所の公園以外で)喫煙、喫煙者を一方的に排除しようとしている市の方針は見直すべきですよ」
さらに言えば川崎市は年間約99億円ものたばこ税収入(令和6年度見込み)がある。市の指定喫煙所の新設、増設や民間の喫煙所設置、運営に対する補助金の財源は十分あるはずだ。これに対する市の考え方は<たばこ税は特定の目的に充てる財源ではなく、広く様々な事業に使われる一般財源であり、たばこ政策だけに使われる性質の税金ではありません>と、木で鼻をくくったような回答をしている。もちろん、たばこ政策だけに使われる税金ではないが、一般会計に回ったたばこ税収の一部を分煙環境整備にあてがうことは十分可能で、東京23区内の自治体では民間事業者への補助を実施しているケースも多い。99億円もの税収があるのだから財源としての活用は十分に可能なはず。